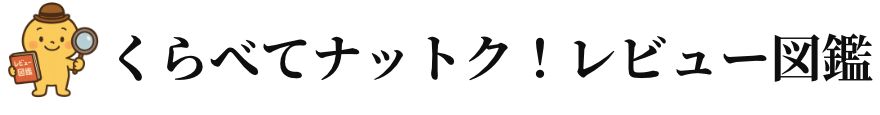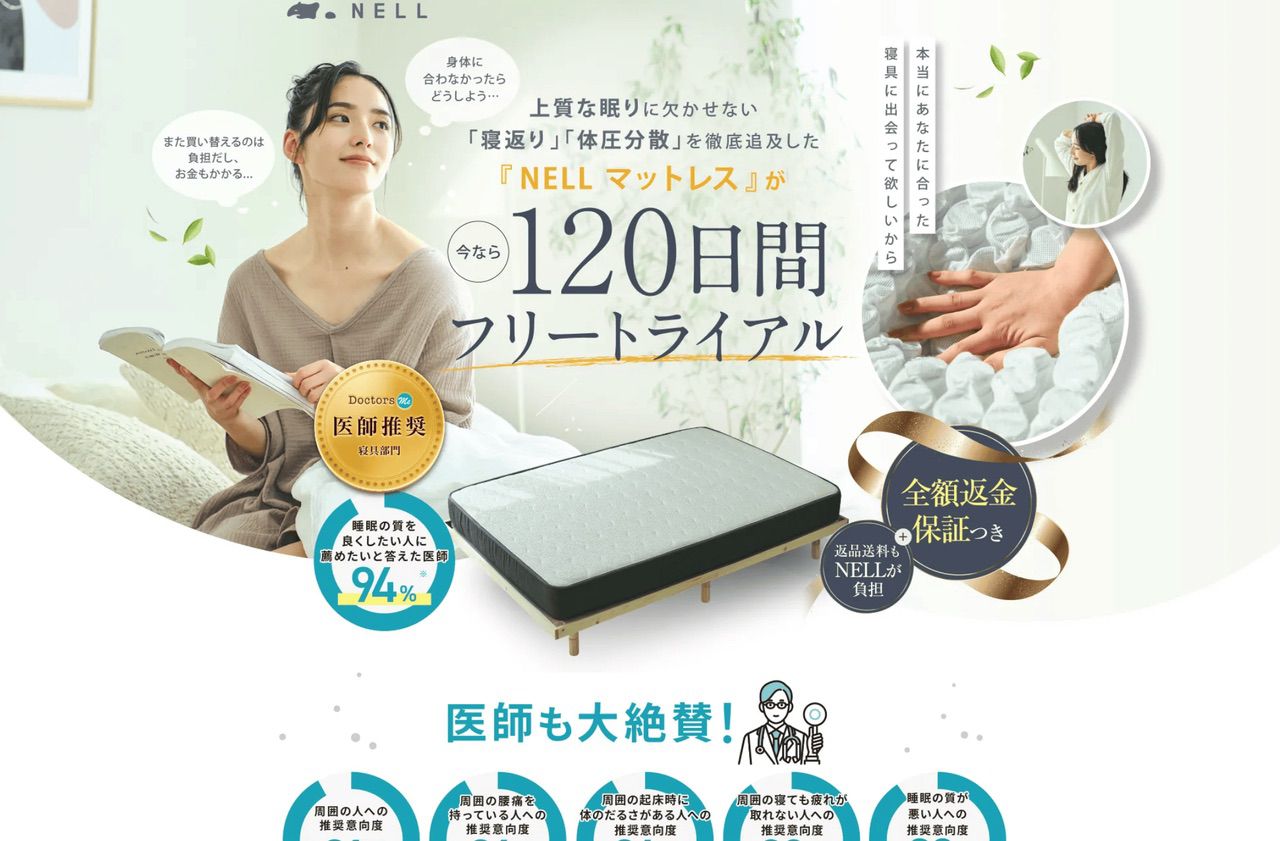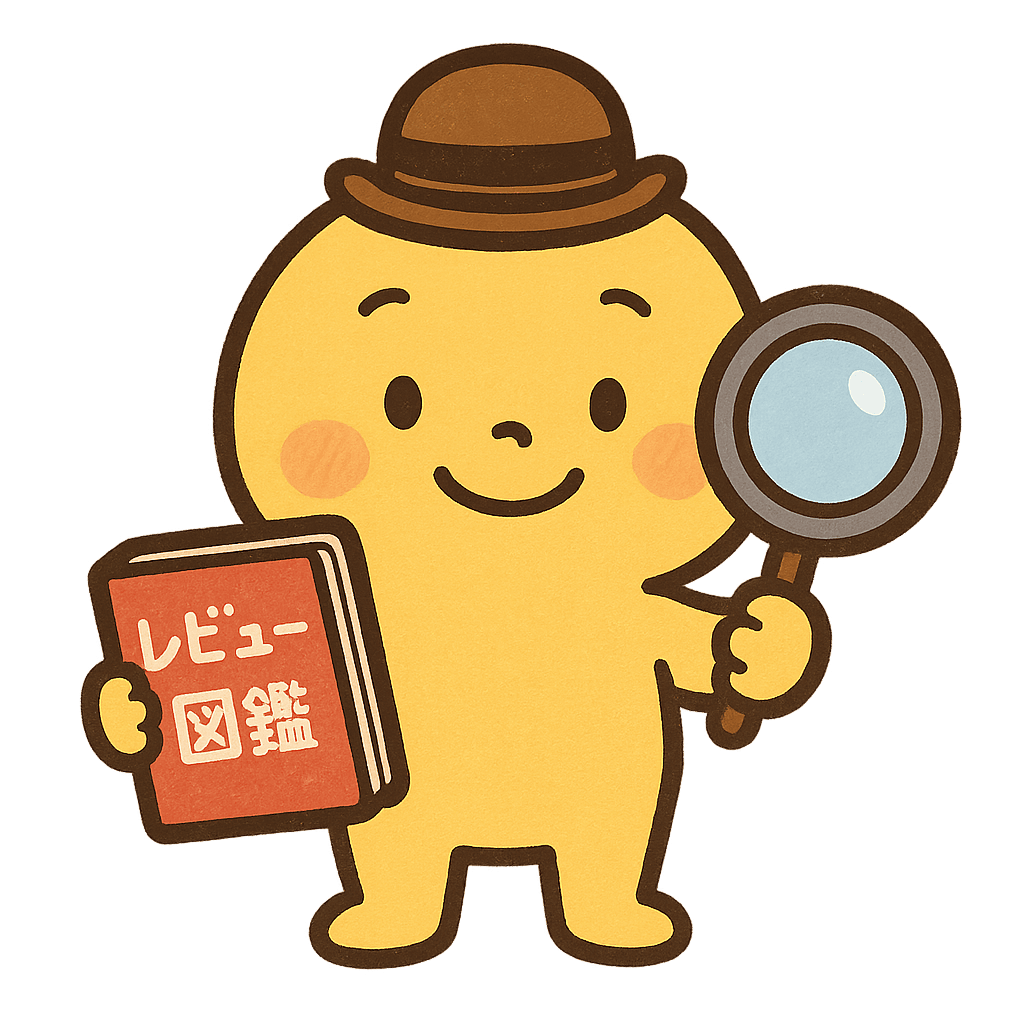
最高の寝心地を追求して作られた、ネルマットレス。
「ベッドフレームって、本当に必要なんだろう?」「床に直置きする使い方じゃダメなのかな?」という大切な悩みどころがありますよね。
せっかくのマットレスだから後悔したくない、でも、できれば余計な出費は抑えたい…。
でも実は、ベッドフレームは、ネルマットレスが持つ本来の性能を最大限に引き出すための、最後の、そして最も重要なピースなんです。
ここでは、あなたのそんな疑問や不安がすべて解消されるように、ベッドフレームの必要性から後悔しない選び方、そして正しい使い方まで、一つひとつ丁寧に解説していきますね。
ネルマットレスにベッドフレームは必要?【結論から解説】
ネルマットレスの購入を考えている皆さま。
最高の寝心地を期待してワクワクしている一方で、「ところで、ベッドフレームって本当に必要なのかな?」「今ある布団みたいに、床に直置きじゃダメなの?」と、ふと疑問に思っていませんか?
実はそれ、すごく大事なポイントなんです。
ここでは、そんなあなたの疑問に結論からズバリお答えしていきますよ。
なぜベッドフレームがあった方が良いのか、その理由を一つひとつ見ていきましょう。
結論:ネルマットレスにはベッドフレームの使用がベストな選択です
はい、結論から言いますね。
ネルマットレスには、ベッドフレームを合わせて使うのがベストな選択です!
もちろん、絶対にないと使えないという訳ではありません。
でも、せっかく手に入れた(もしくは、これから手に入れる)ネルマットレスが持つ本来の性能を100%引き出して、長く清潔に使い続けるためには、ベッドフレームがとっても重要な役割を果たしてくれるんです。
どうせなら、最高の状態で使いたいと思いませんか?
私は、断然その方が良いと思います。
ネルマットレスが持つ本来の通気性を最大限に活かす使い方とは
まず、知っておいてほしいのが、ネルマットレスはすごく通気性に優れたマットレスだということです。
カビやへたりの原因になりやすい厚いウレタンを使わずに、薄いウレタンと不織布を交互に重ねた独自の13層構造を採用しています。
この構造のおかげで、マットレス内部に湿気が溜まりにくくなっているんですよね。
でも、その優れた通気性も、床に直接置いてしまうと空気の逃げ場がなくなってしまって、効果が半減してしまう可能性があるんです。
ベッドフレームで床との間にしっかりとした「空気の通り道」を作ってあげることこそが、ネルマットレスの性能を最大限に活かすための「正しい使い方」と言えるでしょう。
床への直置きはNG?マットレスにカビが生える原因と対策
そもそも、どうしてマットレスにカビが生えやすいかご存知ですか?
カビは「温度(20〜30℃)」「湿度(60%以上)」「栄養分(フケや皮脂など)」の3つの条件がそろうと、一気に繁殖しやすくなります。
私たちは寝ている間にコップ1杯分の汗をかくと言われていて、マットレスはまさにこの湿気を含みやすい状態なんです。
床に直置きすると、この汗からくる湿気がマットレスの底面に溜まり続け、カビにとって最高の環境ができあがってしまいます。
カビが生えたマットレスで寝続けると、アレルギーなどの健康被害につながる可能性もあるので、しっかり予防することが大切ですね。
ベッドフレームがマットレスの寿命を延ばす理由
ベッドフレームの役割は、湿気対策だけじゃないんですよ。
マットレスの同じ部分にばかり体重や湿気が集中するのを防いで、負荷を分散させてくれる役割もあるんです。
これによって、マットレスのへたりを抑え、より長く快適な寝心地をキープすることができます。
ネルマットレスには10年間の耐久保証がついていますが、こうして日々の使い方を少し工夫するだけで、もっと良い状態で長く付き合っていけるはずです。
大切なマットレスを守るための投資と考えると、結果的にコストパフォーマンスも高まるんじゃないかな、と私は思います。
この記事を読めば、あなたに合うベッドフレームの必要性がわかります
ここまで読んでいただいて、「衛生的」「性能の維持」「長持ち」という3つのポイントから、ベッドフレームの必要性を感じていただけたのではないでしょうか。
ベッドフレームは単なる飾りや台ではなく、ネルマットレスの実力を最大限に引き出すための、最高のパートナーなんです。
「なるほど、ベッドフレームが大事なのはわかった!でも、じゃあ一体どんなものを選べばいいの?」
きっと、次にこう思いましたよね?
大丈夫です、次の章からは、ネルマットレスにピッタリ合うベッドフレームの「正しい選び方」を具体的に解説していきますので、ご安心ください!
知らないと後悔するかも?ベッドフレームが必要な3つの理由

前の章でベッドフレームの全体的な必要性についてお話ししましたよね。
ここではさらに一歩踏み込んで、具体的に「どんな良いことがあるのか」を深掘りしていきたいと思います。
知っていると「やっぱりベッドフレームを選んでおいて良かった!」と、きっと納得してもらえるはずですよ。
衛生面や健康面、そして日々の快適性まで、ベッドフレームがもたらしてくれるたくさんのメリットを見ていきましょう。
理由1:カビ・湿気対策でマットレスを清潔に保つ
マットレスにとって、本当に最大の敵と言えるのが「湿気」です。
これはもう、何度言っても言い過ぎることはありません。
ネルマットレスは、厚いウレタンを使わない独自の13層構造で、もともと高い通気性を持っています。
でも、その優れた性能を最大限に引き出してあげて、カビのリスクを最小限に抑えるには、やっぱりベッドフレームでしっかりと空気の通り道を作ってあげることが重要なんです。
寝汗による湿気がカビの温床に
人は睡眠中にコップ1杯分の汗をかく、と言われています。
この汗がマットレスに吸収されて、湿度が60%を超えるとカビの活動が活発になってしまうんです。
もしベッドフレームを使わずに直置きしていると、この湿気はずっとマットレスの底に溜まり続けることになります。
そうなると、カビにとって最高の繁殖環境を提供してしまっているようなものなんですよね。
日本の気候とカビの発生しやすい条件
カビが活発になる温度は20〜30℃くらいとされていて、これはまさに日本の夏の気温とぴったり一致します。
高温多湿な日本の気候は、私たち人間にとっても厳しいですが、カビにとっては天国のような環境なんです。
特に梅雨の時期は本当に注意が必要ですよね。
それに、冬場でも窓の結露などの影響でマットレスの下面が湿ることがあるので、結局のところ、一年中カビ対策は必要だと言えます。
理由2:床上のホコリやハウスダストから睡眠環境を守る
湿気と同じくらい気をつけたい見えない敵、それが「ホコリ」や「ハウスダスト」です。
ベッドフレームを使って寝る位置を少しでも高くすることが、実は健康的な睡眠環境に直結するんですよ。
あまり意識したことがなかった、という人も多いんじゃないでしょうか。
床から30cmはホコリが舞うゾーン
私たちが室内で生活していると、床に溜まったホコリやハウスダストが空気中に舞い上がります。
特に、床から高さ30cmくらいの空間は、最もホコリが浮遊しやすい「ハウスダストゾーン」とも呼ばれているんです。
もしマットレスを直置きしていると、まさにこのゾーンで一晩中呼吸をしながら寝ていることになってしまいます。
そう考えると、ちょっと気になりますよね。
アレルギーが気になる方は特に重要
ハウスダストの中には、ダニの死骸やフン、カビの胞子といった、アレルギーの原因となる物質がたくさん含まれています。
アレルギー性鼻炎やくしゃみ、喘息などの症状をお持ちの方にとっては、寝室の空気をきれいに保つことは本当に大切です。
ベッドフレームを導入して寝床を高くすることは、誰でも手軽に始められる、とても効果的なアレルギー対策の一つと言えるでしょう。
理由3:寝起きの動作が楽になり、腰への負担を軽減する
衛生面だけでなく、日々の体の快適さにもベッドフレームは貢献してくれます。
床に敷いたお布団から「よっこいしょ」と起き上がるのと、ベッドからスッと立ち上がるのでは、腰や膝にかかる負担が全然違うと思いませんか?
特に、朝起きた時に腰に違和感を感じやすい方や、膝が気になる方にとっては、この差はかなり大きいと思います。
ネルマットレスの寝返りのしやすさと組み合わせることで、睡眠中から朝の起床まで、体への負担をぐっと減らすことができますよ。
【理由4】ベッド下のスペースを収納として有効活用できる
これは、特にワンルームにお住まいの方や、お部屋の収納が少ない方には嬉しいメリットじゃないでしょうか。
ベッドフレームを使うことで生まれるベッド下の空間って、実はかなり貴重な収納スペースになるんです。
普段は使わないスーツケースや、季節外れの洋服や家電、来客用のお布団などをしまっておけば、クローゼットに余裕が生まれてお部屋全体がスッキリします。
ただのデッドスペースにしておくのは、もったいないですよね。
【理由5】冬場の床からくる底冷えを防ぎ、快適に眠れる
冬の寒い夜、フローリングに直接マットレスを敷いていると、床からの冷たい空気、いわゆる「底冷え」で体が冷えて、なかなか寝付けない…なんて経験ありませんか?
ベッドフレームで床との間に数十cmの「空気の層」を作ることで、この冷たい空気を遮断する断熱材のような役割を果たしてくれます。
夏は湿気を逃がしてくれて、冬は床からの冷気を防いでくれる。
ベッドフレームは一年を通して、私たちの快適な睡眠をサポートしてくれる、本当に頼もしい相棒なんですよ。
ネルマットレスに合うベッドフレームの正しい選び方【5つの重要ポイント】

ベッドフレームの重要性をご理解いただけたところで、いよいよ本題の「選び方」に入っていきましょう。
「ベッドフレームなんて、どれも同じじゃないの?」と思っているとしたら、それは大きな間違いです。
特に、ネルマットレスの寝心地を最大限に引き出すためには、マットレスとの相性をしっかり考えることが本当に大切なんですよ。
ここでは、ネルマットレスに合うベッドフレームを選ぶための、絶対に外せない5つの重要ポイントを、優先順位の高いものから順番に紹介していきますね!
ポイント1:【最重要】通気性で選ぶなら「すのこ」タイプ一択
ネルマットレスの大きな特徴は、独自の13層構造がもたらす高い通気性です。
この性能を120%活かすためには、ベッドフレームも「通気性」を何よりも最優先で選ぶべきです。
結論から言うと、最もおすすめなのは、間違いなく「すのこ」タイプのベッドフレームですね。
すのこベッドは、マットレスとの接地面に隙間がたくさんあるので、寝汗による湿気を効率的に下へ逃がしてくれます。
まさに、ネルマットレスにとって最高のパートナーと言えるでしょう。
すのこベッドの種類とそれぞれの特徴(桐・檜など)
「すのこ」と一言で言っても、使われている木材によって少しずつ特徴が違うんですよ。
例えば「桐(きり)」は、とても軽くて、湿度を調節する能力に優れているので、湿気の多い日本には最適な素材の一つです。
「檜(ひのき)」は、耐久性が高くて丈夫な上に、リラックス効果のある独特の良い香りがしますよね。
「パイン材(松)」は、比較的リーズナブルなものが多く、木の温かみを感じられるのが魅力です。
それぞれに良さがあるので、ご予算やお部屋の雰囲気に合わせて選んでみてください。
注意!通気性が悪く、避けるべきベッドフレームのタイプとは?
逆に、ネルマットレスとは相性が悪く、避けた方が良いベッドフレームのタイプもあります。
それは、マットレスを載せる面が、隙間のない一枚の板で完全に覆われている「床板タイプ」のものです。
こういったフレームは、せっかくの湿気の逃げ道を完全に塞いでしまいます。
これでは、カビ対策のためにベッドフレームを置く意味がなくなってしまいますからね。
選ぶ際には、必ずマットレスを置く部分の形状を確認するようにしましょう。
ポイント2:ネルマットレスに合う正しい「サイズ」の選び方
これは基本中の基本ですが、意外と見落としがちなポイントです。
マットレスとベッドフレームのサイズは、必ずぴったり合うものを選びましょう。
サイズが合っていないと、マットレスがずれたり、フレームの隙間に落ち込んだりして、寝心地が悪くなるだけでなく、マットレスが傷む原因にもなってしまいます。
長く快適に使うためにも、サイズ選びは慎重に行いましょう。
シングルからキングまで|ネルマットレスのサイズ展開を確認
まずは、ネルマットレスの正確なサイズをしっかりと確認しておきましょう。
シングルは、幅95cm × 長さ195cmです。
セミダブルは、幅120cm × 長さ195cmです。
ダブルは、幅140cm × 長さ195cmです。
クイーンは、幅160cm × 長さ195cmです。
そしてキングは、幅190cm × 長さ195cmとなっています。
ベッドフレームを探すときは、この寸法に適合するかを必ず確認してくださいね。
フレーム選びで失敗しないための採寸のコツ
マットレスのサイズだけでなく、お部屋にベッドフレームがきちんと置けるかどうかの確認も、購入前に絶対にしておきましょう。
チェックすべきは、ベッドフレーム自体の「外寸(外側の寸法)」です。
マットレスより一回り大きいのが普通なので、商品ページでしっかり確認してください。
フレームを置きたい場所の広さを測って、ドアやクローゼットが開けられるか、人がスムーズに通れるスペースが確保できるかを確認しておくと、「買ったのに置けない!」なんて悲劇を防げますよ。
ポイント3:きしみ音を防ぐ「頑丈さ(耐荷重)」の確認方法
寝返りをうつたびにベッドが「ギシギシ…」と鳴ったら、気になって安眠できませんよね。
そうならないために重要なのが、そのベッドフレームがどれくらいの重さまで耐えられるかを示す「耐荷重」です。
耐荷重が低いと、きしみ音が出やすかったり、最悪の場合は壊れてしまったりする可能性もあります。
目安としては、「寝る人の体重の合計 + マットレスの重量」よりも、余裕のある耐荷重のものを選ぶと安心です。
ちなみにネルマットレスのダブルサイズの重量は31.2kgなので、参考にしてください。
ポイント4:ライフスタイルに合う「高さ」の選び方
ベッドフレームの高さは、お部屋の印象や日々の使い勝手を大きく左右するポイントです。
床に近い「ロータイプ」は、天井が高く見えてお部屋に開放感が生まれます。
逆に、ある程度の高さがある「ハイタイプ」は、ベッドからの立ち上がりが楽で、腰や膝への負担が少ないのがメリットですね。
ネルマットレスは、端の部分が硬めのコイルで補強されているので、ベッドの縁に腰掛けやすいのも特徴です。
ベッドに腰掛けたときに、膝がちょうど直角に曲がるくらいの高さが、一般的に体に負担が少ないとされていますよ。
ポイント5:部屋の雰囲気と使い方に合う「デザイン・機能性」で選ぶ
さて、ここまでの実用的なポイントを押さえたら、最後はあなたの好みやライフスタイルに合わせて、デザインや便利な機能を選んでいきましょう!
毎日使うものだからこそ、「これがいい!」と心から思えるお気に入りの一台を見つけたいですよね。
いくつか代表的な機能を紹介しますので、自分に必要かどうかを考えてみてください。
ヘッドボード・宮棚の有無とメリット・デメリット
「ヘッドボード」は、枕がずり落ちるのを防いでくれたり、壁に寄りかかって読書をしたりするのに便利です。
「宮棚(みやだな)」と呼ばれる棚が付いているタイプなら、メガネやスマートフォン、読みかけの本などをちょっと置くスペースとして活躍してくれます。
ヘッドボードがないシンプルなフレームに比べて、少しだけ場所を取るのがデメリットかもしれませんが、それ以上にメリットは大きいと思いますよ。
スマホの充電に便利!コンセント付きフレームの選び方
宮棚にコンセントが付いていると、寝ている間にスマートフォンの充電ができて、本当に便利ですよね。
今や、必須の機能と考えている人も多いんじゃないでしょうか。
購入する前には、コンセントの差し込み口の数や、ベッドフレームから伸びる電源コードの長さが、お部屋のコンセントの位置までちゃんと届くかを確認しておくと、より安心です。
収納付きベッドフレームは本当に必要?選ぶ際の注意点
お部屋の収納が少ない方にとって、引き出しなどが付いた収納付きベッドフレームは、とても魅力的に見えると思います。
ただし、選ぶ際には一つだけ、絶対に注意してほしいことがあります。
それは、ポイント1で解説した「通気性」です。
収納付きベッドは、構造的に通気性が悪くなりがちなんです。
もし収納付きを選ぶのであれば、マットレスを載せる面が必ず「すのこ仕様」になっているものを探してください。
これが、ネルマットレスと組み合わせるための絶対条件だと覚えておいてくださいね!
効果を最大化!ベッドフレームと合わせたネルマットレスの正しい使い方

あなたにぴったりの最高のベッドフレームが見つかったら、いよいよ快適な睡眠生活のスタートですね!
でも、ゴールはまだもう少し先です。
ここでは、ネルマットレスの寝心地を最大限に引き出して、その最高の状態を一日でも長くキープするための「正しい使い方」と「日々のメンテナンス術」をご紹介します。
どれも難しいことは何一つないので、ぜひ今日からでも取り入れてみてくださいね。
使い方1:ベッドの正しい配置|壁から10cm離して空気の通り道を作る
ベッドをお部屋に置くとき、スペースの都合もあって、ついつい壁にぴったりとくっつけてしまいがちですよね。
でも実はこれ、マットレスの側面や裏側に湿気がこもってしまう原因になるんです。
理想的なのは、ベッドを壁から最低でも10cm以上離して配置することです。
こうするだけで、ベッドの周り全体にしっかりと空気の通り道ができて、マットレスの湿気をスムーズに発散させることができるようになります。
また、冬場に結露しやすい窓際にぴったりつけるのも、湿気の原因になるので避けた方が良いでしょう。
使い方2:敷きパッドの正しい使い方|寝汗からマットレス本体を守る
ネルマットレスの上に直接シーツを敷くのも良いのですが、できればその間に「敷きパッド」を一枚挟んで使うことを強くおすすめします。
敷きパッドは、私たちが寝ている間にかくたくさんの汗が、直接マットレス本体に染み込んでしまうのを防いでくれる、とても大切なフィルター役なんです。
マットレスにカビの栄養源となる皮脂やフケ、髪の毛などが付着するのも防いでくれますよ。
この敷きパッドやシーツは、1〜2週間に1回を目安にこまめに洗濯して、常に清潔な状態を保つように心がけましょう。
使い方3:除湿シートの賢い使い方|湿気が気になる季節の必須アイテム
湿気が特に気になる梅雨の時期や、汗をたくさんかく夏場に、さらにプラスしたいアイテムが「除湿シート」です。
これは、マットレスの下、つまりベッドフレームのすのことマットレスの間に敷くことで、敷きパッドだけでは吸収しきれなかった湿気をぐんぐん吸い取ってくれる優れものです。
防水機能がある「マットレスプロテクター」を使うのも、汗や万が一の飲みこぼしからマットレスを完璧にガードしてくれるので、非常に有効な手段ですよ。
使い方4:マットレスの正しい手入れ|3ヶ月に1度の上下・裏返しを忘れずに
ずっと同じ向きのままマットレスを使い続けていると、どうしても同じ場所にばかり湿気や体重の負荷が集中してしまいますよね。
これを防ぐために、3ヶ月に1度を目安に、マットレスの頭側と足側を入れ替える「ローテーション」や、表と裏をひっくり返すメンテナンスを行いましょう。
ネルマットレスは、表裏どちらでも寝心地が変わらない両面仕様になっているので、このお手入れがとても効果的です。
このひと手間が、カビの発生を抑えるだけでなく、マットレスのへたりも防いでくれるんです。
使い方5:寝室の環境づくり|こまめな換気で湿気を部屋に溜めない
ベッド周りの工夫と合わせて、寝室全体の環境を整えることも、とても大切です。
天気の良い日には窓をこまめに開けて、お部屋の空気を入れ替え、湿った空気を外に逃がしてあげましょう。
また、朝起きてすぐのマットレスは、一晩かいた汗で湿気を含んでいます。
掛け布団をすぐにきれいに整えず、めくったままの状態にして、マットレスの表面をしばらく空気に触れさせて乾燥させる習慣をつけるのがおすすめです。
もし、お部屋の事情でなかなか窓が開けられないという場合は、除湿機を使うのも非常に効果的ですよ。
【徹底比較】ネルマットレスと他社人気マットレス|ベッドフレームとの相性で選ぶならどれ?

ここまでネルマットレスとベッドフレームの関係について詳しく解説してきましたが、「他の人気マットレスの場合はどうなの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
マットレスは各社それぞれ、本当に素晴らしい特徴を持っています。
しかし、その内部構造が違うと、ベッドフレームとの付き合い方も少し変わってくるんです。
ここでは、代表的な人気マットレスとネルマットレスを、「ベッドフレームとの相性」という視点から、あくまで中立的な立場で比較していきますね。
| 商品名 | 特徴 | 構造 | 素材 | 価格帯 | 通気性・防臭抗菌性能 | 硬さ | 返品・交換・トライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【NELL マットレス】 |
高密度ポケットコイルで体圧分散に優れ、寝返りしやすい設計 | ポケットコイル+ウレタンフォーム | 高密度ポケットコイル、ウレタンフォーム | 約75,000円~ | 通気性良好、防カビ・抗菌加工あり | 中程度 | 120日間トライアル、10年保証 |
| エマスリープ | 3層構造で体圧分散と通気性を両立 | 3層ウレタンフォーム | エアグリッド、HRXフォームなど | 約98,000円~ | 通気性高く、抗菌カバー使用 | 中程度 | 100日間トライアル、10年保証 |
| コアラマットレス | 振動吸収性に優れ、パートナーの動きを感じにくい | 3層ウレタンフォーム | クラウドセル、テンセルリヨセル繊維 | 約82,000円~ | 通気性良好、抗菌カバー使用 | 表裏で硬さ調整可能 | 120日間トライアル、10年保証 |
| 雲のやすらぎプレミアム
|
5層構造で体圧分散性と保温性を両立 | 5層ウレタンフォーム | 高反発ウレタン、羊毛など | 約39,800円~ | リバーシブル設計で通気性と保温性を調整、防ダニ・抗菌加工あり | やや柔らかめ | 100日間返金保証 |
| 腰痛対策マットレス【モットン】
|
高反発ウレタンで腰痛対策に特化 | 単層ウレタンフォーム | ナノスリー高反発ウレタン | 約39,800円~ | 通気性高く、防ダニ・抗菌加工あり | 硬さ3種類から選択可能 | 90日間トライアル、14日以内返品可 |
| 眠りの世界に品質を【エアウィーヴ公式オンラインストア】
|
エアファイバー素材で高い通気性と体圧分散性 | エアファイバー | ポリエチレン樹脂 | 約66,000円~ | 通気性抜群、カバーと中材洗濯可能 | やや硬め | 30日間返品保証 |
| 「睡眠の質を整える」快眠マットレス!昭和西川のムアツ
|
凹凸構造で体圧を点で支える | 2層ウレタンフォーム | ウレタンフォーム(抗菌加工) | 約49,500円~ | 通気性良好、抗菌・防臭加工あり | やや硬め | 返品保証なし |
比較のポイントは「マットレスの構造」と「通気性」
今回の比較で注目したいポイントは、とてもシンプルです。
それは、マットレスの「構造」と、それによって決まる「通気性」です。
マットレスの構造は、大きく分けると、内部にバネ(コイル)が入っている「コイル系」と、ウレタンフォームなどの素材でできている「フォーム系」があります。
この構造の違いが、湿気の逃しやすさ、つまりベッドフレームの必要性に大きく関わってくるんです。
それぞれのマットレスがどちらのタイプなのかを知ることが、相性の良い使い方を見つけるための鍵になりますよ。
ネルマットレスとベッドフレームの相性
まず基準となるネルマットレスは、ポケットコイルを1,000個以上も密に敷き詰めた「コイル系」のマットレスです。
コイルを使っている最大のメリットは、マットレスの内部に空気の通り道がたくさんあるため、構造的に通気性が非常に高いことです。
そのため、湿気がこもりにくく、カビの発生リスクを抑えることができます。
もちろん、その優れた性能を最大限に引き出すためには、すのこタイプのベッドフレームを使うのがベストな選択であることに変わりはありません。
エマスリープマットレスとベッドフレームの相性
エマスリープは、様々な種類のウレタン素材を重ね合わせた「フォーム系」のマットレスです。
体を包み込むようなフィット感や、体圧分散性に優れているのが特徴ですね。
その一方で、フォーム系のマットレスは内部にコイルのような空洞がないため、湿気が溜まりやすいという側面も持っています。
そのため、湿気を効率的に逃がすためのすのこベッドは、単に推奨されるというよりも、長く快適に使うための「必須アイテム」と考えるのが良いでしょう。
公式サイトでも、清潔で乾燥した場所で使うことや、すのこを下に敷くことがカビ対策として推奨されています。
コアラマットレスとベッドフレームの相性
コアラマットレスも、独自開発のウレタンフォームなどを使用した「フォーム系」のマットレスです。
振動吸収性に優れていて、隣で寝ている人の動きが伝わりにくいのが大きな魅力ですよね。
構造的にはエマスリープと同様に、通気性を確保するためにオープンセル構造などを採用していますが、やはりフォームであることに変わりはありません。
公式サイトでも「通気性を確保するために、スノコのような丈夫なベッドフレームのご使用をおすすめします」と明記されており、すのこベッドとの併用が前提とされています。
雲のやすらぎプレミアムとベッドフレームの相性
雲のやすらぎプレミアムは、ウレタンや羊毛など複数の素材を重ねた、厚さ17cmの極厚なマットレスです。
分類としては、敷布団に近い「フォーム系」と言えるでしょう。
リバーシブル仕様で、春夏面は通気性の良いメッシュ生地を採用するなどの工夫がされています。
しかし、その厚みゆえに、一度湿気を含むと乾きにくいという特徴も持っています。
そのため、直置きで使う場合は、敷布団と同様にこまめな陰干しが欠かせません。
手間を考えると、やはり通気性を確保できるすのこタイプのベッドフレームと合わせて使うのが、より安心で快適な使い方と言えるでしょう。
モットンとベッドフレームの相性
モットンは、高反発ウレタンフォームを使用した、腰へのサポートに特化した「フォーム系」のマットレスです。
こちらも素材の特性上、湿気を吸収しやすく溜め込みやすいという特徴があります。
公式サイトなどでも、カビ防止のために3日に一度程度の陰干しや、除湿シートの使用が推奨されています。
やはり、湿気が自然に抜けるように、通気性を確保できるすのこベッドと組み合わせて使うのが最も効果的で、推奨される使い方です。
【比較まとめ】ベッドフレームとの相性を一覧でチェック
さて、各マットレスの特徴を比較してきましたが、ここで一度ポイントを整理してみましょう。
ネルマットレスは、ポケットコイル構造による高い通気性が特徴で、すのこベッドと組み合わせることでその性能を最大限に発揮します。
エマスリープ、コアラマットレス、モットンといったウレタンフォーム系のマットレスは、寝心地の良さが魅力ですが、湿気がこもりやすいため、すのこベッドは必須と言えるでしょう。
雲のやすらぎプレミアムは、敷布団の快適さとマットレスの厚みを両立していますが、その分、湿気対策はより重要になり、すのこベッドの使用が強く推奨されます。
どのマットレスを選ぶにしても、ベッドフレーム、特にすのこベッドが快適な睡眠環境を維持するための重要な鍵となることが、お分かりいただけたのではないでしょうか。
ネルマットレスとベッドフレームのよくある質問

さて、ここまでベッドフレームの必要性から選び方、そして日々の使い方まで、かなり詳しく解説してきました。
でも、「自分の場合はどうなんだろう?」といった、個別の細かい疑問もまだ残っているかもしれませんね。
この章では、そんな皆さんの「あとちょっとだけ知りたい!」という疑問にお答えする、よくある質問コーナーをお届けします。
これで、あなたの悩みもきっと解消されるはずです。
Q1. どうしても床に直置きしたい場合の正しい使い方はありますか?
お部屋の広さや構造上の問題で、どうしてもベッドフレームを置くのが難しい、という方もいらっしゃいますよね。
直置きは基本的におすすめしませんが、もしそうせざるを得ない場合は、とにかく湿気対策を徹底することが絶対条件になります。
例えば、マットレスの下に直接「すのこ」を敷くだけでも、床との間に空気の層ができて通気性は格段に向上します。
そして、最低でも月に1回はマットレスを壁に立てかけて、裏面にしっかりと風を通してあげてください。
除湿シートをマットレスの下に敷くのも、とても有効な手段ですよ。
Q2. ネルマットレス公式サイトで、合うベッドフレームは販売されていますか?
「公式のものが一番安心できるのに…」と思いますよね。
2025年9月現在、ネルマットレスの公式サイトを調べてみたところ、残念ながら専用のベッドフレームは販売されていないようです。
でも、ご安心ください!
この記事でご紹介した「選び方の5つのポイント」、特に「通気性の良いすのこタイプ」で「サイズが合う」もの、という基準で選べば、市販のベッドフレームの中からでも、ネルマットレスにぴったりの一台を必ず見つけることができますよ。
Q3. 推奨されていない、合わないベッドフレームの種類はありますか?
はい、あります。
これは大切なことなので何度かお伝えしていますが、やはり「通気性」がすべてです。
そのため、マットレスを載せる面が、隙間のない一枚の板でできている「床板タイプ」のベッドフレームは、ネルマットレスには合わないので避けるべきです。
また、ベッド下が引き出しになっている「収納付きベッド」も、その構造上、通気性が悪くなりがちです。
もし収納付きを選ぶ場合は、必ずマットレスを載せる部分が「すのこ仕様」になっているかどうかを確認してくださいね。
Q4. 保証期間内にカビが生えたら、保証の対象になりますか?
これは、とても気になる重要なポイントだと思います。
ネルマットレスには安心の「10年間の耐久保証」がついていますが、これは主に、3cm以上の明らかな「へたり」が生じた場合が対象となります。
一般的に、マットレスに発生するカビは、製品そのものの不具合ではなく、お部屋の湿度やお手入れの状況といった「ご使用環境」が主な原因と考えられています。
そのため、残念ながら保証の対象外となってしまうケースがほとんどです。
だからこそ、カビを発生させないための日々の予防、つまりベッドフレームを正しく使ってお手入れをすることが、本当に大切になってくるんです。
Q5. 今使っているベッドフレームは、ネルマットレスにも合いますか?
すでにベッドフレームをお持ちの場合、わざわざ買い換えるのはもったいないと感じますよね。
もちろん、条件さえ合えば、今お使いのものをそのまま活用できますよ。
チェックしてほしいポイントは3つです。
まず1つ目は、マットレスを載せる部分が、通気性の良い「すのこ仕様」になっているかどうか。
2つ目は、これから購入するネルマットレスのサイズと、フレームの内寸がぴったり合っているかどうか。
そして3つ目は、フレーム自体がまだ丈夫で、新しいマットレス(例えばダブルサイズで31.2kgです )とあなたの体重をしっかりと支えられる状態かどうか。
この3つの条件、特に通気性の部分をクリアしていれば、問題なく使える可能性が高いですよ。
Q6.ネルマットレスに合うベッドフレームはどのようなものですか?
ネルマットレスの性能を最大限に引き出すためには、通気性の良い「すのこ」タイプのベッドフレームが最もおすすめです。
マットレスから発散される湿気を効率的に逃がすことができます。
また、マットレスのサイズに合ったもので、ご自身の体重とマットレスの重量を合わせた重さに十分耐えられる、頑丈なものを選びましょう。
この記事で解説した「選び方の5つのポイント」を参考に、あなたにぴったりの一台を見つけてくださいね。
Q7.ネルマットレスはすのこを使用しても良いですか?
はい、もちろんです。
すのこタイプのベッドフレームは、使用しても良いというよりも、最も推奨される組み合わせです。
ネルマットレスは、内部に空気の通り道が多いポケットコイル構造で、もともと通気性に優れています。
その長所を最大限に活かし、湿気を防いで長く快適に使い続けるために、ぜひすのこタイプのベッドフレームと合わせてお使いください。
Q8.ネルマットレスの上下・表裏はどのように違いますか?
ネルマットレスは、表裏どちらでも寝心地が変わらない「両面仕様」となっています。
そのため、定期的なメンテナンスとしてマットレスを裏返しても、寝心地に影響はありません。
マットレスのへたりや湿気が同じ場所に集中するのを防ぐためにも、3ヶ月に1度を目安に、頭側と足側を入れ替えるローテーションと合わせて、裏返しを行うことをおすすめします。
Q9.ネルマットレスは無印のベッドフレームに合いますか?
特定のメーカーのベッドフレームに合うかどうかは、サイズと仕様によって決まります。
まず、無印良品で販売されているベッドフレームのサイズ(シングル、ダブルなど)が、お使いになるネルマットレスの寸法(幅×長さ)と一致しているかをご確認ください。
その上で、マットレスを載せる面が、通気性の良い「すのこ仕様」のものであれば、問題なくお使いいただけると考えられます。
購入前に、必ず両方の製品の仕様を詳しく確認してくださいね。
Q10.ネルマットレスは子供や赤ちゃんにも使えますか?
一般的に、赤ちゃんの窒息リスクなどを避けるため、ベビーベッドには大人用とは違う、赤ちゃん専用の硬めのマットレスの使用が推奨されています。
ある程度体が大きくなったお子様については、ご使用は可能かと思われますが、体格や寝心地の好みもございます。
より詳しい情報については、公式サイトから直接問い合わせて確認することをおすすめします。
Q11.ネルマットレスは4人家族でどのように使えばいいですか?
ご家族4人で川の字で寝るような使い方を想定されている場合、マットレスを2台連結する方法が一般的です。
例えば、ダブルサイズ(幅140cm)を2台並べれば、合計で幅280cmとなり、4人でもゆったりと眠れるスペースを確保できます。
また、キングサイズ(幅190cm)とシングルサイズ(幅95cm)を組み合わせるなど、お部屋の広さやご家族の体格に合わせて、最適な組み合わせを検討してみてください。
Q12.ネルマットレスは電気毛布を使っても大丈夫ですか?
NELLマットレスの公式FAQによると「耐熱試験を行っているため、問題なくご使用いただけます。」と明記されています。
ただし、過剰な加熱などによってマットレスがダメージを受けた場合は保証対象外となってしまいますので「自己責任での使用」という事に注意してください。
ウレタンフォームなどの素材は、高温に長時間さらされると劣化が早まることがあります。
どうしても寒い場合は、マットレスの上に厚手の敷きパッドを敷いたり、保温性の高い掛け布団を使ったりといった工夫で、暖かさを保つことをおすすめします。
Q13.ネルマットレスを2段ベッドの上で使えますか?
ネルマットレスは、すべてのサイズで厚さが21cmとなっています。
2段ベッドの上段でご使用になる場合は、ベッドの安全柵の高さを必ずご確認ください。
安全基準を満たすためには、マットレスの上面から柵の最上部まで、十分な高さが確保されている必要があります。
また、マットレスの重量(シングルサイズで22.0kg)を考慮し、2段ベッドの耐荷重の範囲内であるかも合わせて確認してください。
Q14.ネルマットレスの10年耐久保証の対象は?日常使いでの凹みは対象になりますか?
ネルマットレスの10年耐久保証は、通常のご使用方法で、マットレスに3cm以上の「へたり(凹み)」が発生した場合が対象となります。
この基準を満たす凹みが確認された場合、保証期間内であれば無料で修繕または交換が行われます。
そのため、3cm未満の日常使いで生じる自然な凹みは、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。
また、この保証は公式サイトなど、正規の販売店から購入した場合にのみ適用されます。
まとめ:最適なベッドフレームで、ネルマットレスの寝心地を最大限に!
ここまで、本当に長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。
ネルマットレスとベッドフレームの関係について、その必要性から具体的な選び方、そして日々の使い方まで、詳しく解説してきました。
もうお分かりいただけたかと思いますが、ベッドフレームは単なるマットレスの土台ではありません。
湿気やカビから大切なマットレスを守り、ネルマットレスが持つ本来の性能を最大限に引き出し、長く清潔に使い続けるための、かけがえのない「最高のパートナー」なんです。
たくさんポイントがあって難しく感じたかもしれませんが、一番大切なのは、やはり「通気性」、つまり「すのこ」タイプのフレームを選ぶこと、ただこれだけです。
このポイントさえ押さえておけば、きっとあなたに合う、後悔のない一台を見つけられるはずですよ。
そして、もしあなたがまだネルマットレスの購入を迷っているのなら、ぜひ一度試してみてほしいなと思います。
ネルマットレスには、自宅でじっくりと寝心地を試せる120日間の返金保証トライアルが用意されています。
もし体に合わないと感じた場合でも、返品の送料は無料なので、安心して最高の寝心地を体験することができます。
あなたも最適なベッドフレームを見つけて、ネルマットレスとの最高の睡眠生活をスタートさせてくださいね。
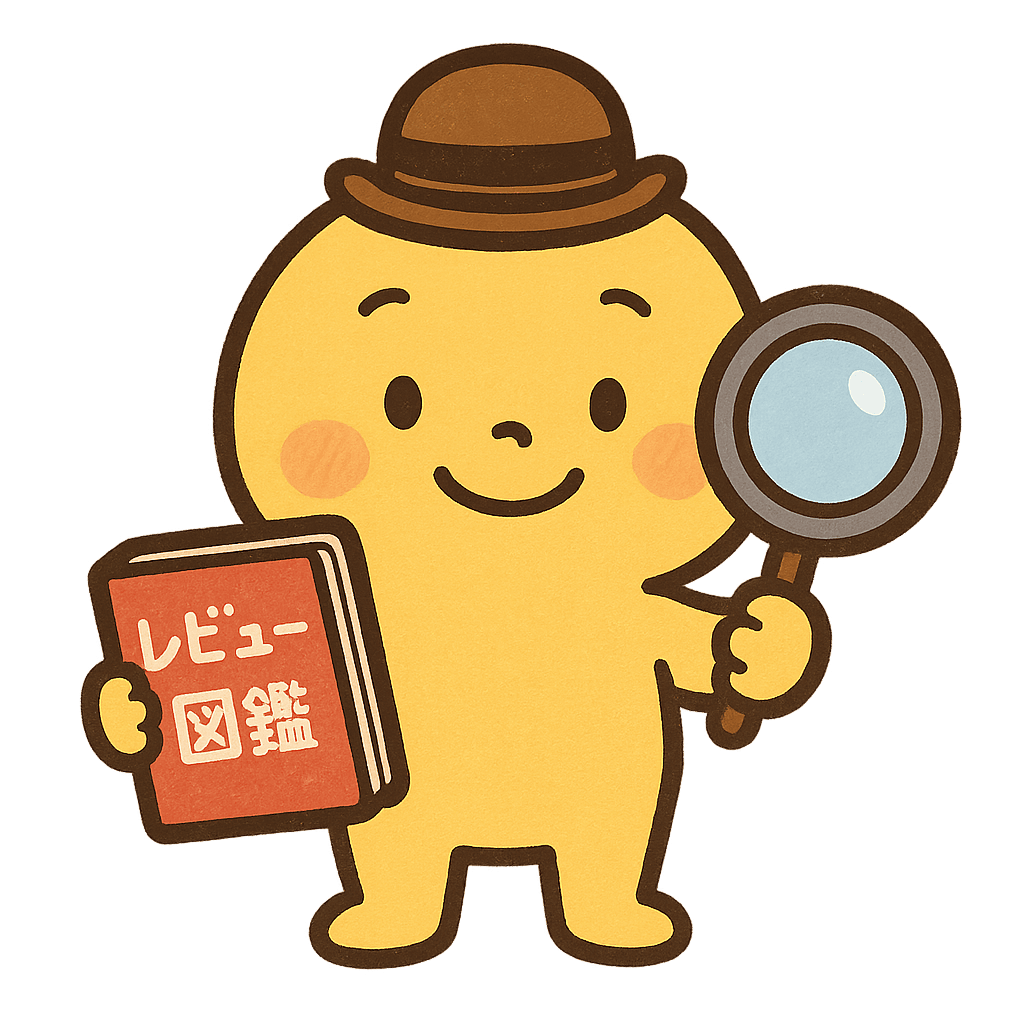
今回、ネルマットレスとベッドフレームの関係について改めて深掘りしてみて、強く感じたことがあります。
それは、最高のマットレスを選ぶのと同じくらい、その土台であるベッドフレームとの相性も大切なんだな、ということです。
私たちはついマットレス本体の寝心地にばかり注目してしまいますが、その性能を陰で支える「縁の下の力持ち」が、まさにベッドフレームなんですね。
最高の睡眠は、最高の寝具と、それを活かす最高の環境づくりから始まるんだなと、改めて実感しました。