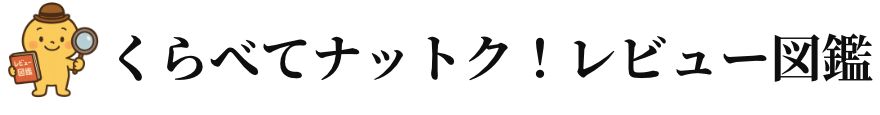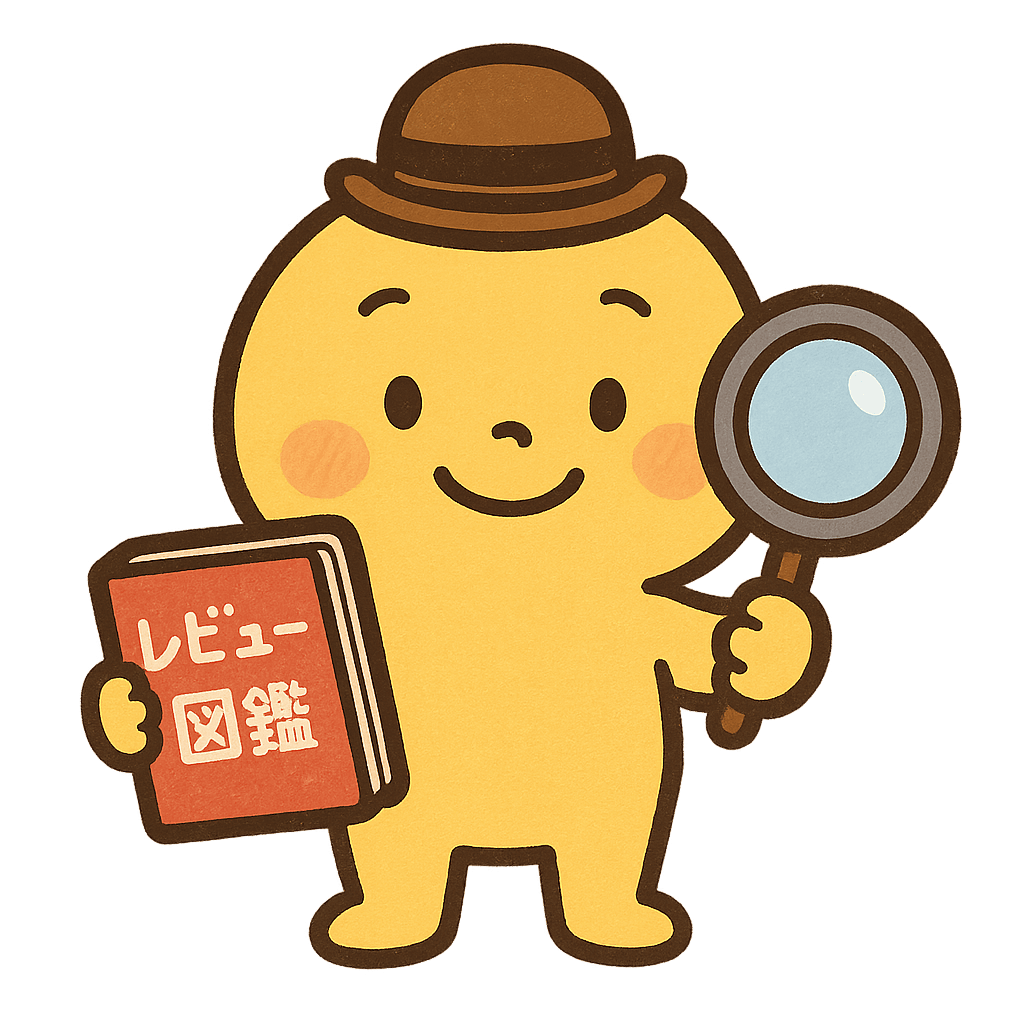
愛犬の健康を願って、評判の良い「カナガン」を選んだのに、全く口を付けてくれない…。
そんな愛犬の姿を見ると、「どうして?」「うちの子には合わなかったのかな?」と不安になったり、がっかりしてしまったりしますよね。
この記事では、トイプードルや子犬がカナガンを食べない時に考えられる原因を徹底的に分析し、今日からすぐに試せる具体的な解決策まで、順を追って分かりやすく解説します。
カナガンを子犬・トイプードルが食べないのはなぜ?考えられる主な原因
愛犬の健康を考えて、栄養満点のカナガンを選んだのに、全く口をつけてくれないと「どうして?」と不安になってしまいますよね。
特に、食が細い子が多いトイプードルや、まだ体の小さい子犬だと、心配はさらに大きくなると思います。
でも、安心してください。
ドッグフードを食べない原因は、単に「味が嫌い」というだけではなく、実はさまざまな理由が考えられるのです。
フードの切り替えに戸惑っているのかもしれませんし、もしかしたら何か体調のサインを送っている可能性もゼロではありません。
ここでは、カナガンを愛犬が食べない時に考えられる主な原因を、一つひとつ丁寧に解説していきます。
原因を正しく理解することが、解決への大切な第一歩になりますから、焦らず一緒に考えていきましょう。
フードの切り替えに慣れていない
もしかしたら、愛犬はまだ新しいフードに慣れていないだけかもしれません。
犬はもともと警戒心が強い動物なので、今まで食べていたフードと匂いや形、食感が違うと、「これ、食べても大丈夫なのかな?」と戸惑ってしまうことがあるんですよね。
特に、繊細な性格の子が多いトイプードルや、まだ食の経験が浅い子犬にとっては、フードの変更はちょっとした一大事なんです。
私たち人間からすると、新しい味は楽しみの一つですが、犬にとっては必ずしもそうとは限りません。
飼い主さんとしては「美味しくないのかな?」と心配になるかもしれませんが、実は「知らない食べ物だから怖い」と感じているだけの可能性も十分に考えられます。
まずは、愛犬が新しい環境に慣れるための時間が必要なんだ、と少しだけ気長に構えてあげるのが良いのかもしれませんね。
新しいフードへの警戒心
犬が新しいフードに対して警戒心を持つのは、野生で暮らしていた頃の本能的な名残だと言われています。
知らないものを口にして、もし毒があったら命に関わりますから、慎重になるのは当然のことなんですね。
その本能が、ペットとして暮らす現代の犬たちにも引き継がれているというわけです。
特にトイプードルのような賢い犬種は、観察力も鋭いので、ちょっとした変化にも敏感に気づきます。
「いつもと違う匂いがする…」「なんだか形が違うぞ…」と感じ取って、なかなか口をつけようとしないことがあります。
また、飼い主さんが「食べてくれるかな?」と心配そうに見つめていると、その緊張感が愛犬に伝わって、さらに警戒心を強めてしまうという悪循環に陥ることもあるようです。
まずは飼い主さんがリラックスして、「これは美味しいごはんだよ」という安心感を伝えてあげることが大切だと思います。
正しい切り替え方法とは?
新しいフードへの切り替えは、焦らずゆっくりと進めるのが成功の秘訣です。
いきなり100%カナガンにしてしまうと、愛犬もびっくりしてしまいますからね。
おすすめなのは、今まで食べていたフードに、ほんの少しだけカナガンを混ぜてあげる方法です。
初日は、今までのフードを9割、カナガンを1割くらいの割合から始めてみましょう。
それを問題なく食べてくれるようなら、次の日はカナガンの割合を2割に、その次の日は3割に…といった具合に、だいたい7日から10日くらいかけて、少しずつ割合を増やしていきます。
この時、うんちの状態をしっかりチェックしてあげることも重要です。
もし、うんちが緩くなってしまうようなら、一度割合を元に戻したり、変化のペースをさらにゆっくりにしてあげてください。
愛犬の体のペースに合わせて、じっくり慣らしていくことが、結局は一番の近道になるはずです。
食べ物の好みやわがまま
犬にも、私たち人間と同じように、食べ物の好き嫌いがあるのはご存知でしょうか。
特に、トイプードルのような賢い犬種は、「これを食べなければ、もっと美味しいものが出てくるはず!」と学習してしまうことがあるんです。
ごはんを食べない時に、心配のあまりおやつをあげたり、人間の食事を分け与えたりした経験はありませんか?。
その優しい行動が、結果的に「ごはんを食べなければ、もっと良いことがある」と愛犬に教えてしまっている可能性があるのです。
もちろん、愛犬が可愛くてつい甘やかしたくなる気持ちは、私もすごくよく分かります。
ですが、愛犬の健康のためには、時には心を鬼にして、食事のルールをきちんと教えることも大切になってきます。
わがままが原因でフードを食べないのであれば、それはしつけの問題として捉え、根気強く向き合っていく必要があるかもしれません。
グルメなトイプードル・子犬の傾向
トイプードルが「グルメだ」とか「食にうるさい」と言われるのには、いくつか理由があるようです。
もともと小型犬で、一度にたくさんの量を食べる犬種ではないため、食が細く見えやすいという特徴があります。
また、非常に賢い犬種なので、味や食感の違いにも敏感で、自分の好みをはっきりと持っている子が多いんですね。
子犬の頃の食生活も、将来の食習慣に大きく影響します。
もし、子犬の時から茹でたささみやお肉などをトッピングしたごはんに慣れていると、それが当たり前になってしまい、ドライフードだけでは物足りなく感じてしまう子もいるようです。
また、毎日同じフードだと飽きてしまう、という人間のような感覚を持つ犬も実際にいます。
カナガンにはチキン味とサーモン味があるので、もし片方を食べないのであれば、もう一方の味を試してみるのも良い方法かもしれませんね。
「もっと美味しいものが出てくる」という学習
犬の学習能力は、私たちが思っている以上に高いものですよね。
特に「これをしたら良いことがあった」という経験は、驚くほど強く記憶に残ります。
フードを食べなかった時に、飼い主さんが心配して「じゃあ、代わりにこれをあげるね」と、おやつや果物などを与えたとします。
すると犬は、「ごはんを残せば、もっと美味しい特別なものがもらえるんだ!」と、あっという間に学習してしまうのです。
一度この学習が成立してしまうと、なかなか手強く、毎回ごはんの時間になると、より良いものを期待してフードを食べずに待つようになってしまいます。
このループを断ち切るためには、まず食事の時間をきちんと決めることが大切です。
フードを出して、例えば15分から30分ほど経っても食べないのであれば、一度食器を片付けてしまいましょう。
そして、次の食事の時間まで、おやつなどは一切与えないようにします。
最初は可哀想に思うかもしれませんが、ここで毅然とした態度をとることが、結果的に愛犬の健康的な食生活を守ることにつながるのです。
体調不良や病気の可能性
いつもは食いしん坊な愛犬が、急にフードを食べなくなった時は、少し注意が必要かもしれません。
もしかしたら、それは「ちょっと体調が悪いよ」という愛犬からのサインである可能性があるからです。
人間も、風邪をひいたりお腹の調子が悪かったりすると、食欲がなくなりますよね。
犬も全く同じで、体のどこかに不調を抱えていると、まず食欲が落ちることが多いんです。
特に、見た目には分かりにくい内臓の病気や、口の中に痛みがある場合(歯周病など)でも、食欲不振という症状で現れることがあります。
「ただのわがままかな?」と軽く考えずに、食欲以外の変化がないか、愛犬の様子を注意深く観察してあげることが大切です。
フードを食べないこと以外に、何かいつもと違う様子が見られる場合は、早めに動物病院に相談することをおすすめします。
食欲不振は体調のサインかも
食欲不振は、さまざまな病気の初期症状として現れることが知られています。
例えば、胃腸炎や消化不良といった消化器系のトラブルはもちろんのこと、感染症や内臓疾患、ストレスなどが原因で食欲が落ちることも少なくありません。
特に子犬の場合は、まだ体力や免疫力が十分ではないため、環境の変化によるストレスなど、ささいなことでも体調を崩しやすい傾向があります。
また、見落としがちなのが口の中のトラブルです。
乳歯から永久歯に生え変わる時期(歯がむず痒い時期)や、歯周病で歯茎が痛む場合、「食べたいけど、口が痛くて食べられない」という状況に陥っている可能性もあります。
フードを食べたそうにするけれど、口に入れてもすぐに吐き出してしまう、といった行動が見られる場合は、口の中を一度チェックしてあげると良いでしょう。
愛犬は言葉で不調を訴えることができない分、私たち飼い主が日々の小さな変化に気づいてあげることが何よりも重要になります。
注意すべき他の症状
愛犬がフードを食べない時、同時に以下のような症状が見られないかを確認してみてください。
これらは、何らかの病気が隠れているサインかもしれません。
・元気がない、ぐったりしている
・下痢や嘔吐を繰り返す
・水をたくさん飲む、または全く飲まない
・おしっこの色や量、回数がいつもと違う
・震えている、どこか痛そうにしている
・よだれの量が多い、口臭が強くなった
これらの症状が一つでも見られる場合は、様子を見ずに、できるだけ早く動物病院を受診してください。
特に、子犬やシニア犬は容体が急変することもありますので、早期の対応が肝心です。
獣医師に相談する際は、「いつから食べないのか」「他の症状は何か」「うんちやおしっこの状態」などを具体的に伝えられるように、メモしておくと診察がスムーズに進みます。
何事もなければそれで安心できますし、飼い主さんの不安を解消するためにも、専門家の意見を聞くことはとても大切です。
フードの与え方や環境の問題
意外と見落としがちなのが、食事を与える時の環境や、フードの与え方そのものに問題があるケースです。
もしかしたら愛犬は、フード自体が嫌いなのではなく、「なんだかこの場所では落ち着いて食べられないな」と感じているのかもしれません。
例えば、食事場所が人の通り道にしっちゅうになっていたり、テレビの音が大きすぎたり、他のペットがちょっかいを出してきたりする環境では、臆病な子や集中したいタイプの子は、安心して食事に専念することができません。
また、食器の素材や高さが体に合っていないために、食べにくさを感じている可能性も考えられます。
さらに、私たち飼い主の行動が、無意識のうちに愛犬の食欲を削いでしまっていることもあるんです。
愛犬が快適に食事を楽しめるように、一度、食事周りの環境全体を見直してみるのも良い方法だと思います。
食器や場所は適切?
まず確認してみたいのが、食事をする場所です。
犬が安心して食事をするためには、静かで落ち着けるパーソナルスペースを確保してあげることが理想的です。
部屋の隅など、人の行き来が少ない場所に専用の食事スペースを設けてあげましょう。
次に、食器についてです。
ステンレス製の食器は、匂いがつきにくく衛生的ですが、フードを入れる時にカチャカチャと音が鳴るのを嫌がる繊細な子もいます。
また、プラスチック製の食器は軽くて扱いやすいですが、傷がつきやすく、その傷に雑菌が繁殖しやすいというデメリットもあります。
陶器製の食器は、重さがあって安定し、汚れも落としやすいのでおすすめです。
さらに、食器の高さも重要なポイントです。
特にトイプードルのような首の長い犬種は、床に直接置かれた食器だと、首を大きく曲げなければならず、食べにくいだけでなく、体に負担がかかることもあります。
台座付きのフードボウルなどを使って、少し高さを出してあげると、楽な姿勢で食べられるようになり、食欲が増すケースも少なくありません。
飼い主の態度が影響することも
愛犬の食事中、飼い主さんがすぐ側でじーっと見つめていたり、「食べなさい」とプレッシャーをかけたりしていませんか?。
「食べてくれるか心配…」という気持ちからくる行動だとは思うのですが、実はこれが逆効果になっていることがあるんです。
犬によっては、食事中に監視されているようで落ち着かず、食べるのをやめてしまうことがあります。
また、食事の時間が、飼い主さんにかまってもらえる時間だと学習してしまうと、食べるふりをして気を引こうとする子もいるようです。
食事の時間は、あまり過干渉にならず、少し離れた場所からそっと見守るくらいの距離感がちょうど良いのかもしれません。
フードを準備したら、「ごはんよ」と声をかけて、あとは愛犬のペースに任せてみましょう。
飼い主さんがリラックスして、食事の時間を「楽しいもの」として演出してあげることで、愛犬も安心してフードを口にするようになるのではないでしょうか。
おやつの与えすぎで満腹になっている
愛犬がカナガンを食べない原因として、とてもシンプルですが、意外と多いのが「おやつの与えすぎ」です。
特に、食事の直前におやつをあげてしまうと、それだけでお腹が満たされてしまい、メインのごはんが食べられなくなってしまうのは当然のことですよね。
私たち人間でも、夕食の前にポテトチップスを一袋食べてしまったら、美味しいご馳走を目の前にしても、あまり食欲がわかないのと同じだと思います。
しつけのご褒美や、コミュニケーションの一環としておやつはとても有効なツールですが、与える量やタイミングには少し注意が必要です。
愛犬の一日の摂取カロリーのうち、おやつが占める割合は10%程度に抑えるのが理想的だと言われています。
もし、ごはんを食べないことで悩んでいるなら、一度、一日のおやつの量や与える時間帯を見直してみることをおすすめします。
おやつの適正量を知ろう
では、具体的に「おやつの適正量」とはどのくらいなのでしょうか。
一般的には、犬が一日に必要とする総カロリーの10%以内が目安とされています。
例えば、一日に500キロカロリー必要な犬であれば、おやつで摂取して良いカロリーは50キロカロリーまで、ということになります。
しかし、おやつのパッケージに記載されているカロリー表示は、商品によって様々で、いちいち計算するのは少し大変ですよね。
簡単な方法としては、まずメインで与えているドッグフード(カナガン)の一日の給与量を確認し、その給与量の10%分をおやつに置き換える、という考え方があります。
例えば、一日の給与量が100gなら、そのうちの10g分を減らして、その減らした分のカロリーに相当するおやつを与える、というイメージです。
ジャーキーやビスケットなど、市販のおやつは意外と高カロリーなものが多いので、与える量には注意が必要です。
野菜や果物などを少量おやつ代わりにするのも、カロリーを抑える良い方法だと思います。
食事の前の時間は特におやつを控える
おやつの量を調整することに加えて、もう一つ気をつけたいのが「与えるタイミング」です。
当たり前のことかもしれませんが、食事の前の2〜3時間は、おやつを与えるのを控えるようにしましょう。
空腹は、最高のスパイスと言いますよね。
食事の時間にちゃんとお腹が空いている状態を作ってあげることが、ドッグフードを美味しく食べてもらうための重要なポイントになります。
もし、しつけのトレーニングなどで、どうしても食事前におやつ(ご褒美)を使いたい場合は、一粒のフードを半分に割るなど、できるだけ少量にとどめる工夫が必要です。
また、おやつをあげる時と、食事を与える時のメリハリをしっかりつけることも大切です。
おやつはあくまで「特別なご褒美」であり、主食は栄養バランスの取れたドッグフードなのだということを、日々の生活の中で愛犬に教えていきましょう。
そうすることで、食事の時間になれば、ちゃんとお腹を空かせて、ごはんを心待ちにしてくれるようになるはずです。
【今日から試せる】カナガンを食べるようになる具体的な対処法5選
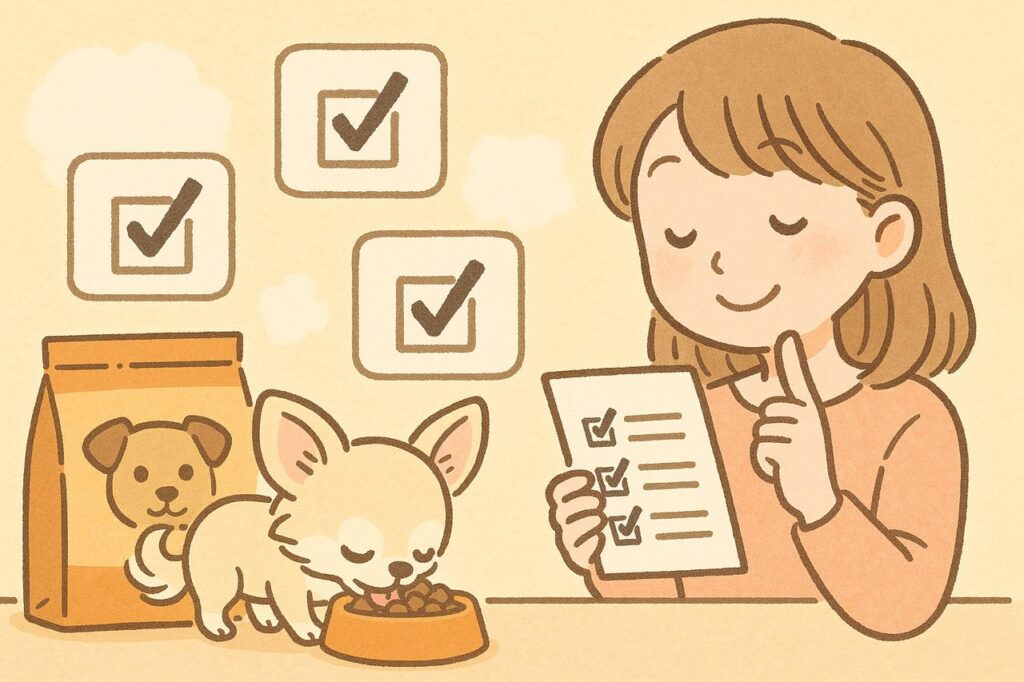
愛犬がフードを食べない原因が、なんとなく見えてきたのではないでしょうか。
原因が分かったら、次はいよいよ具体的な対策を試していくステップです。
ここでは、専門的な知識がなくても、今日からすぐに試せる簡単な対処法を5つに絞ってご紹介します。
「うちの子にはどれが合うかな?」と考えながら、気軽に試せるものからチャレンジしてみてください。
どの方法も、大切なのは飼い主さんが焦らず、リラックスして取り組むことだと思います。
愛犬のペースに合わせて、ゆっくり進めていきましょう。
きっと、あなたの愛犬にピッタリな方法が見つかるはずです。
今までのフードに少しずつ混ぜて慣らす
まず最初に試していただきたい、最も基本的で効果的な方法がこちらです。
前のセクションでも少し触れましたが、警戒心の強いワンちゃんにとって、いきなり全く新しいごはんに変わるのは大きなストレスになります。
そこで、今まで食べていた慣れ親しんだフードに、新しいカナガンをほんの少しだけ混ぜてあげることから始めます。
こうすることで、慣れた匂いの中に新しい匂いが少しだけ混ざった状態になるので、愛犬も安心して口をつけやすくなるんですね。
いわば、新しい友達を紹介する時に、まずは共通の友達を介して会うようなものかもしれません。
この方法は、お腹がデリケートな子が、新しいフードで下痢をしてしまうのを防ぐ効果も期待できます。
時間は少しかかりますが、愛犬の心と体の両方に負担をかけない、とても優しい方法だと言えます。
切り替えの黄金比率スケジュール
フードを切り替える際の比率は、愛犬の様子を見ながら調整するのが一番ですが、ここでは一般的な目安となるスケジュールをご紹介します。
全体で7日から10日くらいかけて、ゆっくり移行するのが理想的です。
【1〜2日目】カナガン:10% + 今までのフード:90%
まずは「新しいごはんの匂いがするな」と認識してもらうくらいの少量からスタートします。
【3〜4日目】カナガン:25% + 今までのフード:75%
問題なく食べてくれるようなら、少しだけカナガンの割合を増やしてみましょう。
【5〜6日目】カナガン:50% + 今までのフード:50%
ここでちょうど半々になります。
うんちの状態も引き続きチェックしてください。
【7〜8日目】カナガン:75% + 今までのフード:25%
ここまでくれば、あと一息です。
ほとんどカナガンになっても、美味しそうに食べてくれるか観察します。
【9日目以降】カナガン:100%
ついに切り替えが完了です。
もし途中で食いつきが悪くなったり、うんちが緩くなったりした場合は、焦らずに一つ前のステップに戻って、その割合を数日間続けてみてください。
愛犬のペースに合わせることが、何よりも大切です。
ぬるま湯でふやかして香りを立たせる
ドライフードの食いつきが悪い時に、ぜひ試してほしいのが、フードをぬるま湯でふやかす方法です。
犬は人間よりもずっと嗅覚が優れている動物なので、「香り」は食事の満足度に大きく影響します。
ドライフードをぬるま湯でふやかすと、素材の香りがふわっと引き立ち、犬の食欲を強く刺激してくれるんです。
特にカナガンは、上質なチキンやサーモンをたっぷり使っているのが特徴なので、この方法で香りを引き出してあげるのは非常に効果的だと思います。
袋を開けた時の、あの芳醇な香りがさらに強くなるイメージですね。
また、食感が柔らかくなることで、食べやすさが向上するというメリットもあります。
普段と少し違う特別感も出て、愛犬の興味を引くことができるかもしれません。
手軽にできるのに、効果は抜群なことが多いので、試してみる価値は大きいですよ。
ふやかし方の正しい手順と温度
フードをふやかす、と聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、手順はとても簡単です。
まず、いつもの量のカナガンを食器に入れます。
次に、フードがひたひたに浸るくらいの「ぬるま湯」を注ぎます。
ここでのポイントは、必ず「ぬるま湯」を使うことです。
温度の目安は、だいたい30℃から40℃くらい、人間のお風呂くらいの温度が最適です。
熱湯をかけてしまうと、フードに含まれる熱に弱いビタミンなどの栄養素が壊れてしまう可能性があるので、絶対に避けてください。
ぬるま湯を注いだら、そのまま5分から10分ほど置いておきます。
表面が少し柔らかくなった状態から、芯まで完全にふやけた状態まで、どのくらいの硬さが好みかは愛犬によって違うので、色々試してみてください。
最後に、与える前には必ず指で触って、熱すぎないかを確認してあげましょう。
衛生面を考えて、作り置きはせず、必ず食事の都度作るようにしてくださいね。
子犬やシニア犬にもおすすめの理由
この「ぬるま湯でふやかす」方法は、実は子犬やシニア犬(老犬)にとって、特におすすめできる食べ方なんです。
子犬は、まだ永久歯が生えそろっていなかったり、あごの力が弱かったりするため、硬いドライフードをそのまま食べるのが難しい場合があります。
ふやかしてあげることで、食べやすくなるのはもちろん、消化の助けにもなるので、まだ消化器官が未発達な子犬のお腹にも優しいんですね。
一方、シニア犬は、年齢と共に歯が弱くなったり、飲み込む力が衰えてきたりします。
そんなシニア犬にとっても、柔らかくふやかしたフードは非常に食べやすい食事になります。
また、ドライフードは水分量が少ないですが、ふやかすことで食事と同時に自然な形で水分補給ができるのも、シニア犬にとっては大きなメリットです。
年齢を問わず、全てのワンちゃんにおすすめできる、体に優しい工夫だと言えるでしょう。
食欲をそそるトッピングを試してみる
いろいろ試しても、どうしても食いつきが改善しない…。
そんな時の、いわば「最終手段」として考えたいのが、フードへのトッピングです。
いつものフードに、愛犬が好きな食材を少量加えてあげることで、香りが豊かになり、食欲を刺激する効果が期待できます。
トッピングは食いつきを劇的に改善する可能性がある一方で、注意も必要な方法です。
なぜなら、トッピングの味を覚えてしまうと、「トッピングがないと食べない」という、さらなるわがままに繋がってしまう可能性があるからです。
大切なのは、主食はあくまで栄養バランスが計算された総合栄養食であるカナガンだ、ということを忘れないことです。
トッピングは、例えるならご飯にかける「ふりかけ」のようなもの。
主食の味を邪魔しない程度に、少量だけ添えてあげるという意識で活用するのが良いと思います。
ドッグフードに合うおすすめの食材
トッピングに使う食材は、犬が食べても安全で、栄養面でもプラスになるものを選びたいですよね。
ここでは、手軽に用意できて、ドッグフードとの相性も良いおすすめの食材をいくつかご紹介します。
・鶏のささみや胸肉(茹でて、細かくほぐしたもの)
高タンパク低脂肪で、香りも良いので犬に大人気です。
・無糖のプレーンヨーグルト
腸内環境を整えるのを助ける働きが期待できます。
与えすぎるとお腹が緩くなる子もいるので、最初はティースプーン1杯程度から試してください。
・カボチャやさつまいも(加熱して、ペースト状にしたもの)
自然な甘みがあり、食物繊維も豊富です。
・すりおろしたリンゴ
酵素やビタミンを手軽にプラスできます。
芯や種は必ず取り除いてください。
・ウェットフード
ドライフードと同じブランドのウェットフードを少量混ぜるのも、香りが増して食いつきが良くなる簡単な方法です。
これらの食材を、ほんの少しだけフードに混ぜ込んであげてみてください。
トッピングをする際の注意点
愛犬の喜ぶ顔が見たいからと、ついたくさんトッピングしたくなる気持ちも分かりますが、いくつか守ってほしい大切な注意点があります。
まず、トッピングの量は、一日の食事全体の10%以内にとどめるようにしてください。
これ以上多くなると、カナガンの優れた栄養バランスが崩れてしまう原因になります。
次に、犬にとって中毒となる危険な食材は、絶対に与えないでください。
ネギ類(玉ねぎ、長ネギなど)、チョコレート、ぶどう、アボカドなどは、犬が食べると命に関わることもあるので、厳禁です。
味付けも一切不要です。
塩分や糖分の過剰摂取は、犬の健康を害する原因となります。
そして最も大切なのが、トッピングを「当たり前」にしないことです。
「食欲がない時だけのスペシャルメニュー」といったルールを決め、普段はカナガンだけで食べられるように習慣づけていくことが、長期的な健康管理のためには重要になります。
食事の環境を見直して集中させる
フードを食べない原因が、実は食事をする環境にある、というケースも少なくありません。
私たち人間も、騒がしい場所や落ち着かない場所では、ゆっくり食事を楽しめないことがありますよね。
犬はもっと敏感なので、周囲の環境が気になって食事に集中できていない可能性があります。
特に、子犬や臆病な性格の子は、物音や人の動きに気を取られがちです。
「うちの子、食べるのが下手だな」と思っていたら、実は集中できる環境が整っていなかっただけ、ということもあり得ます。
フードそのものを工夫する前に、一度、愛犬が毎日食事をしている場所や状況を客観的に見直してみませんか?。
ほんの少し環境を変えてあげるだけで、驚くほど食いつきが改善されることもあるんですよ。
静かで落ち着ける場所を用意する
愛犬の食事スペースは、どこに設置していますか?。
もし、家族が頻繁に通る廊下や、テレビの目の前など、騒がしい場所に食器を置いているのであれば、場所を変えてあげることを検討してみてください。
犬が食事に集中できる理想的な場所は、「静かで、落ち着ける、少し囲まれた空間」です。
例えば、部屋の隅や、ケージ・サークルの中などがおすすめです。
そこを愛犬専用の「レストラン」にしてあげることで、「ここは安心してごはんが食べられる場所だ」と学習してくれます。
多頭飼いの場合は、他の犬に邪魔されないように、少し離れた場所で食事をさせる配慮も必要です。
他の犬の存在がプレッシャーになって、ゆっくり食べられない子が意外と多いんです。
それぞれのパーソナルスペースを尊重してあげることで、どの子も安心して自分の食事に集中できるようになります。
安心してリラックスできる環境は、美味しいごはんをさらに美味しく感じさせてくれるスパイスになるはずです。
「ながら食べ」はさせない
フードを食器に入れたまま、一日中置きっぱなしにしていませんか?。
いつでも食べられるようにという優しさからかもしれませんが、この「ながら食べ」の習慣は、食事への集中力を欠いてしまう原因になります。
食事のメリハリがなくなり、「今食べなくても、お腹が空いたらまた食べればいいや」と思ってしまうんですね。
その結果、少量ずつダラダラと食べるようになり、一回の食事で満足感を得にくくなってしまいます。
食事の時間は、きちんと決めて、メリハリをつけることが大切です。
フードを出したら、15分から30分ほどの時間を区切り、もし食べなくても一度食器を下げてしまいましょう。
そして、次の食事の時間までは、何も与えないようにします。
これを繰り返すことで、「ごはんはこの時間しか食べられないんだ」と学習し、出された時に集中して食べるようになります。
衛生的にも、フードを長時間出しっぱなしにしておくのは良くありません。
食事の時間を「特別な時間」として認識させてあげることが、食いつきを良くするためのしつけの一環にもなるのです。
おやつの量やタイミングを調整する
最後に確認したいのが、おやつの与え方です。
これは、前のセクションの原因の部分でも触れましたが、食いつきに直接影響する非常に重要なポイントなので、対処法としても改めて解説させてください。
可愛い愛犬についあげたくなってしまうおやつですが、その量やタイミングが、主食であるカナガンを食べない原因になっている可能性は十分に考えられます。
特に、少量でも満足感の高いおやつは、知らず知らずのうちに愛犬のお腹を満たしてしまっています。
食事の前に「お腹がいっぱい」の状態であれば、いくら美味しいフードでも食べられないのは当然ですよね。
愛犬の健康的な食生活のためには、おやつはあくまで補助的なものとして捉え、主食とのバランスをしっかり考えることが大切です。
もう一度、一日のおやつの全体量と、与えるタイミングを見直してみましょう。
ご褒美とおやつの違いを理解する
おやつと一括りに言っても、その役割にはいくつか種類があると思います。
一つは、トイレの成功や「お手」などのコマンドができた時に与える「ご褒美」としての役割です。
これは、しつけのトレーニングにおいて非常に有効で、犬のモチベーションを高めるために必要不可欠なものです。
もう一つは、飼い主さんとのコミュニケーションや、単純な「お楽しみ」として与えるおやつです。
問題なのは、この二つの境界線が曖昧になってしまい、特に理由もなく、飼い主さんの気分で頻繁におやつを与えてしまうことです。
「ご褒美」として与える場合は、ボーロ一粒や、フードを数粒だけ、といった少量でも犬は十分に喜びます。
コミュニケーションとして何かを与えたいのであれば、必ずしもおやつである必要はなく、撫でてあげたり、褒めてあげたりすることでも、犬は愛情を感じ取ってくれます。
おやつを「特別なもの」として位置づけ、与える際のルールを明確にすることが、量やタイミングをコントロールする第一歩になります。
食事への影響が少ないおやつの与え方
では、具体的にどのようにすれば、食事に影響を与えずにおやつを活用できるのでしょうか。
まず、基本中の基本ですが、食事の直前(少なくとも2〜3時間前)にはおやつを与えないようにしましょう。
おやつをあげるベストなタイミングは、食後や、日中の運動・トレーニングの後などです。
また、一日に与えるおやつの量をあらかじめ決めておき、小さな容器などに入れて管理するのもおすすめです。
「今日のおやつはこれでおしまい」と可視化することで、うっかり与えすぎてしまうのを防ぐことができます。
おやつの種類も、なるべく低カロリーで、添加物の少ない自然なものを選ぶと良いでしょう。
そして、もし可能であれば、一日のおやつの分を、主食であるカナガンの給与量から少しだけ減らして調整できると、カロリーコントロールは完璧です。
おやつは、愛犬との生活を豊かにしてくれる素晴らしいツールです。
上手に付き合って、食事の楽しみを邪魔しないように活用していきたいですね。
カナガンの評判は?口コミからわかる食いつきを良くする工夫

「実際にカナガンを試した他のワンちゃんたちは、どうだったんだろう?」と、口コミや評判はやっぱり気になりますよね。
特に、同じトイプードルや子犬を飼っている方の意見は、とても参考になると思います。
そこでここでは、インターネット上で見られるカナガンに対するリアルな口コミを集めて、その傾向を分析してみました。
もちろん、「すごく食べた!」という良い口コミもあれば、「残念ながら食べてくれなかった…」という正直な声もあります。
ここでは、そういった様々な意見を公平にご紹介しながら、口コミの中に隠れている「食いつきを良くするためのヒント」を探っていきたいと思います。
先輩飼い主さんたちの成功例や失敗談から、あなたの愛犬に合った工夫を見つけていきましょう。
良い口コミ「驚くほど食いつきが良くなった!」
カナガンの口コミで、最も多く見られるのが「食いつきがとにかく良い」という喜びの声です。
「今までどんなフードも完食したことがなかったのに、カナガンだけは夢中で食べてくれる」といった意見は、本当にたくさん見つかります。
これは、カナガンが原材料の50%以上をチキンやサーモンといった高品質な動物性タンパク質で作られていることが、大きな理由だと考えられます。
袋を開けた瞬間に広がる、お肉やお魚の自然で芳醇な香りが、ワンちゃんの食欲を強く刺激するのでしょう。
特に、今まであまりフードに興味を示さなかった偏食気味の子や、食が細いトイプードルが、カナガンに変えた途端に完食するようになった、というエピソードは象徴的です。
飼い主さんからは「食事の時間が楽しみになった」「美味しそうに食べる姿を見るのが嬉しい」といった、愛犬の変化を喜ぶ声が多数寄せられていました。
悪い口コミ「うちの子は食べなかった…」その理由とは
一方で、もちろん「期待して買ったのに、全く食べてくれなかった」という残念な口コミも存在します。
どんなに評判の良いフードでも、全ての犬の好みに合うわけではないので、これは仕方のないことかもしれません。
食べなかったという口コミを詳しく見ていくと、いくつかのパターンが見えてきました。
一つは、フードの「匂いが独特で苦手だったようだ」という意見です。
香料を使っていない素材そのものの香りが、逆に一部のワンちゃんには好まれなかったケースがあるようです。
また、「粒が硬くて食べにくそうだった」という声も少数ですが見られました。
歯が弱いシニア犬や、口が小さい超小型犬にとっては、少し工夫が必要な場合があるのかもしれません。
そして、最も多いのが「今まで食べていたフードからの切り替えが上手くいかなかった」というケースです。
これらの口コミからは、やはり新しいフードに慣れるまでのプロセスが、非常に重要であることが改めて分かりますね。
口コミで見つけた!先輩飼い主が実践する裏ワザ紹介
様々な口コミを調べていると、食べなかったワンちゃんに対して、飼い主さんたちが実践している様々な工夫が見つかりました。
まさに、先輩たちの知恵と愛情が詰まった「裏ワザ」と言えるかもしれません。
最も多く試されていたのが、やはり「ぬるま湯でふやかす」という方法です。
これで匂いがさらに強くなり食欲をそそるだけでなく、硬さが気になる子にも食べやすくなるため、多くの方が効果を実感しているようでした。
次に多かったのが、少量の「トッピング」です。
茹でたささみを少しだけ混ぜたり、ヨーグルトをかけたり、といった定番の工夫で食いつきが改善したという声がありました。
ユニークなものでは、「フードを少しだけ手で温めてからあげると香りが立って食べる」という意見や、「フードをお皿に広げて、宝探しのようにしてあげると遊びながら食べる」といった工夫も見られました。
愛犬の性格に合わせて、ゲーム感覚を取り入れてみるのも面白い方法かもしれません。
カナガンのチキンとサーモン、トイプードルにはどっちが人気?
カナガンには、定番の「チキン」と、アレルギーに配慮した「サーモン」の2種類の味があります。
「うちの子には、どちらが合うんだろう?」と悩む方も多いのではないでしょうか。
口コミ全体を見ると、やはり販売実績が長いこともあり、「チキン」に関する口コミの数が圧倒的に多い印象です。
一般的に、犬は鶏肉の風味を好む子が多いと言われており、「チキンの香りで食いつきが抜群だった」という声が多数を占めています。
一方で、「サーモン」を選んだ飼い主さんからは、「チキンアレルギーがあるので助かる」「毛並みが良くなった気がする」といった意見が見られました。
サーモンに含まれるオメガ3脂肪酸が、皮膚や被毛の健康維持に良い影響を与えているのかもしれませんね。
トイプードルは皮膚がデリケートな子も多いので、もしチキンでアレルギーが心配な場合や、毛並みの美しさを特に意識したい場合には、サーモンを試してみる価値は十分にあると言えるでしょう。
まずは王道のチキンから試してみて、愛犬の反応を見るのが一般的なようです。
子犬の初めてのフードとしての口コミ評価
カナガンは全年齢対応なので、子犬の初めての本格的なドライフードとして選ぶ飼い主さんも多いようです。
子犬の飼い主さんからの口コミで目立ったのは、「栄養価が高いので、成長期の体に安心」という声でした。
高タンパクでグレインフリー(穀物不使用)という点が、子犬の体づくりを考える飼い主さんから高く評価されています。
食いつきに関しても、子犬は好奇心旺盛な子が多いからか、「最初からガツガツ食べてくれた」というポジティブな意見がほとんどでした。
ただ、一部で「うんちが少し緩くなった」という口コミも見られました。
これは、栄養価が高いフードに体が慣れていない時に起こりやすい現象です。
ブリーダーさんのところで食べていたフードから切り替える際は、少量ずつ、時間をかけて慣らしてあげるのが特に重要だと言えます。
子犬の頃の食事は、一生の健康の土台を作る大切なものです。
口コミを参考にしつつも、目の前にいる愛犬の体調をしっかり観察しながら進めていくことが大切ですね。
それでもカナガンを食べない時に飼い主ができること

ここまでご紹介した様々な対処法を試してみても、愛犬がどうしてもカナガンを食べてくれない…。
そんな状況だと、飼い主さんとしては「もう、どうしたらいいの…」と途方に暮れてしまいますよね。
でも、まだ諦めるのは早いかもしれません。
フードを食べない背景には、これまで考えてきた原因とは、また別の可能性が隠れていることもあります。
ここでは、あらゆる工夫を凝らしても状況が改善しない時に、飼い主さんとして最後に確認したいこと、そして次に取るべき行動について考えていきたいと思います。
愛犬の健康を守るために、少し視点を変えて、もう一度じっくり原因を探ってみましょう。
時には、専門家の力を借りることも、とても大切な選択肢の一つになります。
アレルギーの可能性を疑う
もしかしたら、愛犬は特定の食材に対してアレルギー反応を起こしているのかもしれません。
食物アレルギーの症状は、皮膚の痒みや下痢・嘔吐などが一般的ですが、中には「なんとなくお腹の調子が悪い」「食後に不快感がある」といった、飼い主さんが気づきにくい症状として現れることもあります。
もし、本能的に「これを食べると、なんだか体の調子が悪くなる」と感じ取っているとしたら、フードを避けるのは当然の行動ですよね。
カナガンのチキン味であれば、主原料は「チキン」です。
もし愛犬が鶏肉アレルギーを持っていた場合、それが食べない原因になっている可能性があります。
最近では、犬のアレルギーも多様化しており、チキンの他に、牛肉や乳製品、小麦、大豆などがアレルゲンとなりやすいと言われています。
もし、フードを食べないこと以外に、体を頻繁に掻いていたり、目や口の周りが赤くなっていたり、下痢をしやすいといった症状が見られる場合は、一度食物アレルギーの可能性を考えてみる価値はあると思います。
他の病気が隠れていないか獣医師に相談する
いろいろな対策を試しても一向に食欲が戻らない、そして、なんとなく元気もないようだ…。
そんな時は、やはり動物病院で獣医師に相談するのが最も確実で安心な方法です。
食欲不振は、私たち飼い主には見えない、体の内側で起きている何らかの病気のサインである可能性が常にあります。
特に、今まで食いしん坊だった子が急に食べなくなった場合は、注意が必要です。
動物病院では、問診や触診、必要に応じて血液検査やレントゲン検査などを行うことで、食欲不振の根本的な原因を突き止めることができます。
もし病気が見つかれば、早期治療につながりますし、逆に「特に体に異常はありませんよ」と診断されれば、それはそれで大きな安心材料になりますよね。
「こんなことで病院に行くのは大げさかな?」などとためらわずに、愛犬の「いつもと違う」という飼い主さんの直感を信じて、気軽に相談してみてください。
フードの保管方法は正しい?風味の劣化をチェック
これは意外と見落としがちなポイントですが、ドッグフードの保管方法が原因で、食いつきが悪くなっている可能性があります。
ドライフードは乾燥しているので長持ちするイメージがありますが、実は非常に繊細な食べ物なんです。
特に、一度開封したフードは、空気中の酸素に触れることで、少しずつ酸化が進んでいきます。
酸化が進むと、フードに含まれる油脂が劣化し、風味が落ちて、犬が嫌う油臭い匂いになってしまうのです。
犬は人間の何倍も嗅覚が優れていますから、私たちには分からないようなわずかな風味の変化にも敏感に気づきます。
「最初はよく食べていたのに、最近になって食べなくなった」という場合は、このフードの劣化が原因かもしれません。
カナガンのような高品質なフードは、保存料を極力使っていない分、保管には特に気をつけたいところです。
袋の口をしっかり閉じて、直射日光が当たらない、湿気の少ない涼しい場所で保管することを徹底しましょう。
カナガンの他のラインナップを検討する
もし、愛犬がカナガンの「チキン」を食べないのであれば、もう一つの選択肢として「サーモン」を試してみるのも、非常に有効な手段です。
単純に、チキンの風味が好みではない、という可能性も十分に考えられます。
人間にも、お肉は好きだけどお魚は苦手、という人がいるように、犬にもそれぞれ味の好みがあるんですね。
カナガンのサーモンは、主原料に上質なサーモンをたっぷり使っており、チキンとは全く違った風味と香りが特徴です。
サーモンに含まれるオメガ3脂肪酸は、皮膚や被毛の健康をサポートする効果も期待できるので、特に毛並みが気になるトイプードルには嬉しい成分だと言えます。
また、前述した「チキンアレルギー」が疑われる場合にも、タンパク源を変えるという意味で、サーモンは試してみる価値が大きいです。
同じブランドのフードなので、栄養バランスの考え方や品質はそのままに、味のバリエーションを変えることができるのは、カナガンの大きな強みの一つだと思います。
思い切って別のフードを探してみる
様々な工夫を試し、獣医師にも相談して体に問題がないことも確認できた。
それでも、どうしてもカナガンを食べてくれない…。
そんな時は、とても残念ですが、そのフードがあなたの愛犬には合わなかった、と判断する勇気も必要です。
どんなに栄養価が高く、評判が良いフードであっても、世界中の全ての犬が喜んで食べるわけではありません。
フード選びで最も大切なのは、ブランドや価格ではなく、「愛犬が毎日喜んで食べてくれて、健康な体を維持できること」です。
カナガンにこだわらず、一度視野を広げて、他のプレミアムドッグフードを探してみるのも、決して悪い選択ではありません。
その際は、今回の経験を活かして、チキン以外のタンパク源を主原料にしたものや、粒の形や硬さが違うものなど、これまでとは違ったタイプのものを選んでみると、良い結果に繋がるかもしれません。
愛犬に合うフードは、必ずどこかにあるはずです。
飼い主さんがフード探しの旅に疲れてしまわないように、焦らず、また新しい気持ちで探してあげてください。
カナガンの与え方に関する疑問を解消!/食べない場合はどうすれば?

ここでは、カナガンの与え方に関して、多くの飼い主さんが疑問に思う点や、よくある質問についてまとめてお答えしていきます。
カロリーや給餌量の目安、子犬に与える際のポイントなど、具体的な情報を知ることで、より安心して愛犬にカナガンを与えることができるようになるはずです。
また、食べない場合の工夫や、正しい保存方法といった、知っておくと役立つ情報もご紹介します。
日々のフードに関するちょっとした疑問や不安を解消するために、ぜひ参考にしてください。
公式サイトのマイページでできることについても解説しますので、すでに利用されている方も、これから利用を考えている方も必見です。
カナガンのカロリーはどのくらいですか?
愛犬の健康管理、特に体重管理をする上で、フードのカロリーはとても気になるところだと思います。
カナガンドッグフードのカロリーは、公式サイトの情報によると「チキン」「サーモン」共に、100gあたり376kcalとなっています。
これは、一般的なプレミアムドッグフードと比較すると、標準的なカロリー値と言えるでしょう。
カナガンは、筋肉の元となる高品質な動物性タンパク質を豊富に含みつつ、犬が消化しにくい穀物を使わないグレインフリーレシピを採用しています。
そのため、必要な栄養を効率よく摂取しながら、健康的な体づくりをサポートできるように考えられています。
高タンパクなレシピは、犬にとって満足感も得やすいと言われています。
もちろん、与えすぎてしまえば体重増加の原因になりますから、次の項目でご紹介する給餌量の目安をしっかりと守ることが大切です。
愛犬の体重や活動量に合わせて、適切なカロリーを摂取できるように心がけてあげましょう。
カナガンの給餌量について年齢や体重別に教えてください
一日に与えるフードの量は、愛犬の健康を維持するための基本ですよね。
カナガンの給餌量は、犬の年齢(月齢)や現在の体重、そして将来予想される体重によって細かく設定されています。
まず子犬の場合ですが、例えば将来的に体重5kgになることが予想されるトイプードルの子犬であれば、生後2ヶ月では一日あたり75g、生後4ヶ月では85gが目安となります。
成長期の子犬は、たくさんの栄養を必要とするため、成犬よりも体重あたりの給餌量が多く設定されているのが特徴です。
次に成犬の場合ですと、体重が5kgの犬であれば、一日あたりの給餌量の目安は75gから115gとなっています。
この幅は、愛犬の運動量によって調整するためのものです。
お家でのんびり過ごすことが多い子であれば少なめに、毎日ドッグランで走り回るような活発な子であれば多めに、といった具合に調整してあげてください。
これらの数値はあくまで目安なので、最終的には愛犬の体型や便の状態をよく観察しながら、その子に合った最適な量を見つけてあげることが何よりも大切です。
カナガンは子犬に与えても大丈夫?
はい、もちろん大丈夫です。
カナガンは、特定の年齢層に限定されたフードではなく、子犬からシニア犬まで、全てのライフステージで食べることができる「全年齢対応」のドッグフードです。
特に、子犬の時期は、骨格や筋肉、内臓など、体全体の基礎が作られる非常に重要な成長期にあたります。
この時期に、どのような栄養を摂取するかが、その後の犬の生涯の健康を左右すると言っても過言ではありません。
カナガンは、良質なチキンやサーモンを主原料とした高タンパクなレシピで、子犬の力強い体づくりをしっかりとサポートしてくれます。
また、犬の消化に負担をかけるとされる穀物を使用していないグレインフリーなので、まだ消化器官が未熟な子犬にも安心して与えることができます。
子犬に与える際は、まだ顎の力が弱く、硬いものが食べにくい場合もあるので、ぬるま湯で少しふやかしてから与えてあげると、より食べやすくなるのでおすすめですよ。
カナガンを食べない場合の工夫を教えてください
愛犬がカナガンを食べない時には、いくつか試していただきたい工夫があります。
この記事の中でも詳しくご紹介してきましたが、ここで簡単におさらいしておきましょう。
まず、最も試していただきたいのが「ぬるま湯でふやかす」方法です。
フードの香りが引き立ち、犬の食欲を刺激する効果が期待できます。
次に、「今までのフードに少しずつ混ぜる」方法も有効です。
特にフードを切り替えた直後に食べない場合は、新しいフードに慣れていないだけの可能性が高いので、1週間から10日ほどかけてゆっくりと切り替えてあげてください。
また、食事の環境を見直し、静かで落ち着ける場所で食べさせてあげることも大切です。
それでも食べない時の最終手段として、茹でたささみや無糖ヨーグルトなどを少量「トッピング」する方法もありますが、これは癖にならないように注意が必要です。
これらの工夫と合わせて、おやつの与えすぎが原因になっていないかも、一度確認してみてください。
カナガンの賞味期限や保存方法は?
フードの品質を保つ上で、賞味期限と保存方法は非常に重要なポイントです。
カナガンの賞味期限は、パッケージの裏面に「日/月/西暦」の順番で印字されています。
例えば「01/10/25」と記載があれば、2025年10月1日が賞味期限となります。
公式サイトによると、未開封の状態であれば製造から18ヶ月間、品質が保たれるようです。
そして、一度開封した後の賞味期限の目安は、約3ヶ月です。
開封後は、フードが空気に触れて酸化が進み、風味が落ちてしまうので、なるべく早めに使い切るようにしましょう。
保存する際は、まずパッケージのジッパーをしっかりと閉めて、空気を抜くことが大切です。
その上で、直射日光が当たる場所や、高温多湿になる場所は避けて、涼しくて風通しの良い場所で保管してください。
冷蔵庫での保管は、出し入れする際の温度差で袋の中に結露が発生し、カビの原因になることがあるので、おすすめされていません。
正しい方法で保管して、いつでも美味しい状態で愛犬に与えてあげたいですね。
カナガンの会員マイページにログインする方法、会員ページで何ができる?
カナガンを公式サイトの定期コースで購入すると、便利な会員専用の「マイページ」を利用することができます。
ログインするには、まずカナガンの公式サイトにアクセスし、サイトの上部やメニュー内にある「ログイン」ボタンを探します。
そこから、登録したメールアドレスとパスワードを入力すれば、簡単にマイページに入ることができます。
このマイページでできることは、非常に多岐にわたります。
例えば、「フードが溜まってきたから、次回のお届けを少し延期したい」といった場合の「次回お届け予定日の変更」や、「愛犬の食べるペースに合わせて、届けてもらう間隔を変えたい」という時の「お届け周期の変更」が可能です。
また、長期の旅行などで家を空ける際には、一時的に定期コースを「休止」することもできます。
その他にも、お届け先の住所の変更や、登録しているクレジットカード情報の更新など、購入に関する様々な手続きを、電話などをすることなく、24時間いつでも自分のタイミングで行うことができるので、とても便利です。
まとめ:カナガンを食べない悩みは工夫次第!焦らず愛犬に合った方法を見つけよう
フードを食べない理由は、単なる「わがまま」や「好き嫌い」だけでなく、フードの切り替えへの戸惑いや、食事環境、体調不良のサインなど、本当に様々だということがわかりました。
大切なのは、「どうして食べてくれないの!」と焦ったり、不安になったりするのではなく、「この子は何を伝えようとしているのかな?」と、愛犬の気持ちに寄り添って、一つひとつ原因を探ってあげることだと思います。
ぬるま湯でふやかしてみたり、食事の場所を変えてみたり、おやつの量を見直してみたり…。
今回ご紹介した工夫の中に、きっとあなたの愛犬に合う方法が見つかるはずです。
それでも解決しない場合は、アレルギーや他の病気の可能性も視野に入れ、獣医師に相談するという選択肢も忘れないでください。
フード選びは、愛犬の健康な毎日を支えるための、飼い主さんにしかできない愛情表現の一つです。
この記事が、あなたの愛犬との食事が、もっと楽しくて幸せな時間になるための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
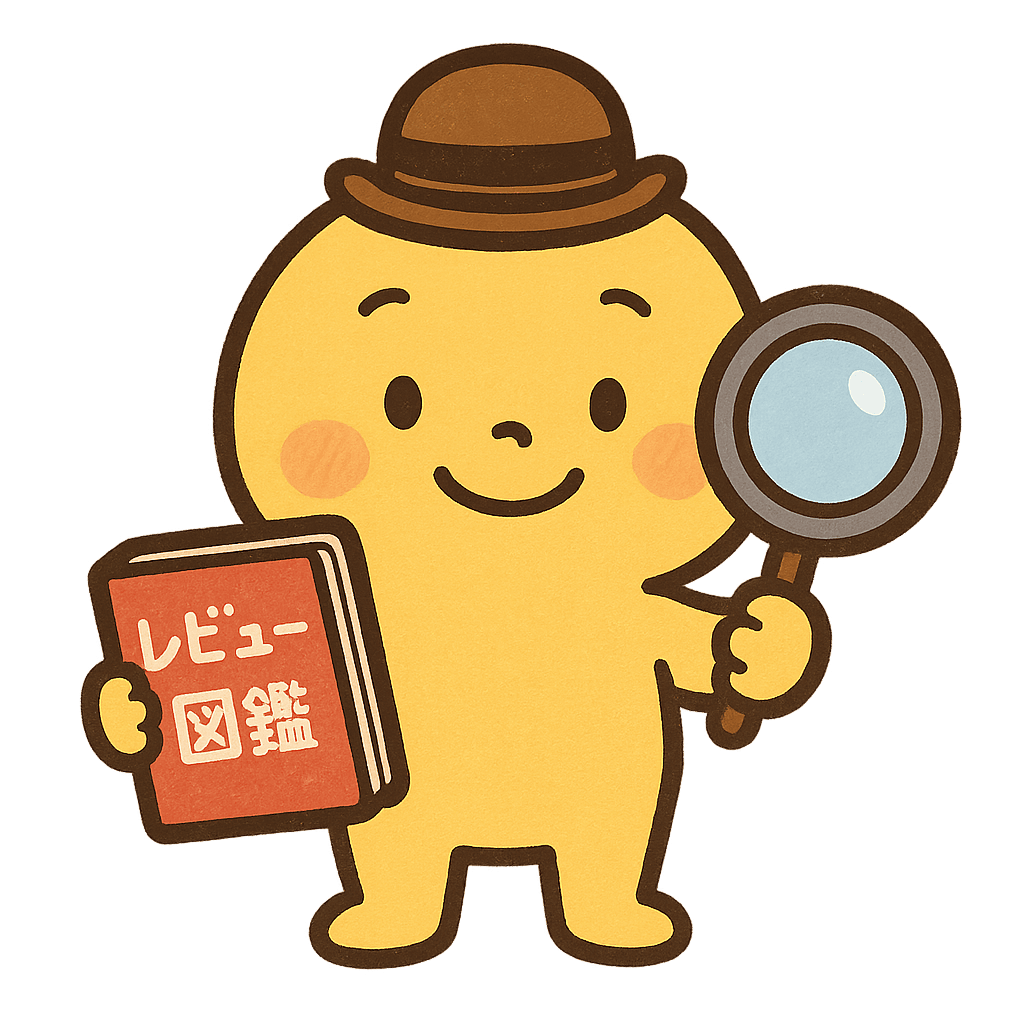
今回、カナガンを食べない原因と対策を改めて深く掘り下げてみて、私自身が一番納得したのは、「犬の食欲は、心と体の状態を映す正直な鏡なのだな」ということでした。
飼い主からすると「わがまま」に見える行動も、実はフードの切り替えに対する戸惑いや、口の中の違和感、あるいは環境へのストレスといった、彼らなりの切実な理由があるんですね。