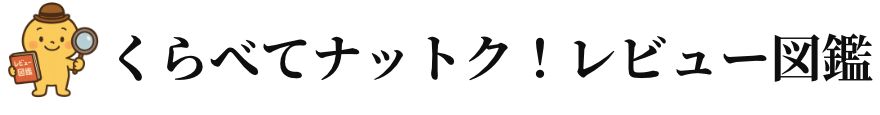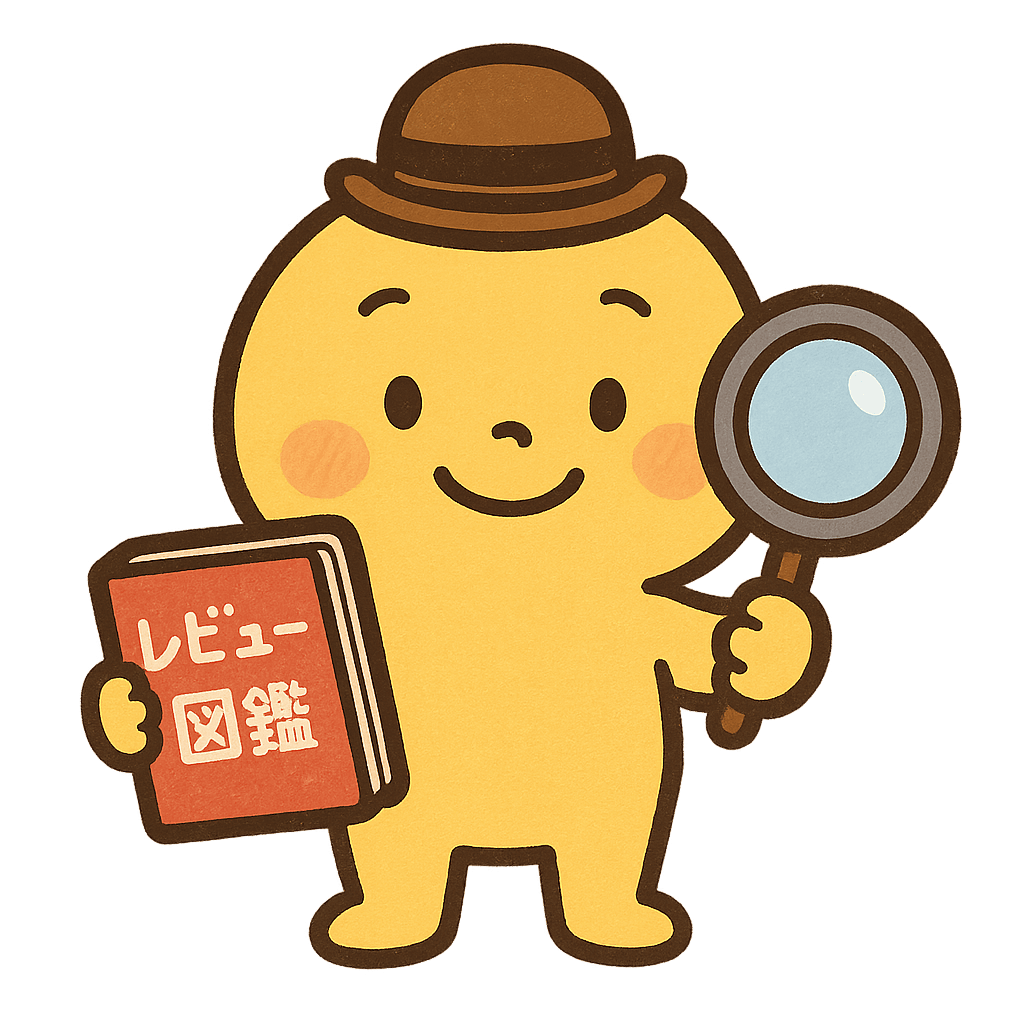
愛犬のドッグフードの量、「本当にこれで合っているかな?」と不安に思ったことはありませんか?
良質なフードを選ぶのと同じくらい、実は「適切な量を与えること」は愛犬の健康にとって非常に重要です。
多すぎれば肥満のリスクが、少なすぎれば栄養不足につながってしまうことも。
この記事では、そんな飼い主さんの尽きない悩みである「カナガンドッグフードの給餌量」に焦点を当て、愛犬にぴったりの量を見つけるための具体的な方法を徹底解説します。
まずは確認!カナガンドッグフードの給餌量の基本
愛犬のためにプレミアムドッグフードを調べていて、カナガンにたどり着いた方は多いのではないでしょうか。
ただ、良さそうなフードなのはわかるけど、「うちの子にはどれくらいの量を与えればいいんだろう?」と、具体的な給餌量が気になりますよね。
フードの量は、多すぎても少なすぎても愛犬の健康に影響してしまう大切なポイントです。
ここでは、まずカナガンドッグフードの給餌量を考える上での基本的な考え方や、公式サイトに載っている給餌量ガイドの正しい見方について解説していきます。
この章を読み終える頃には、給餌量の基本がしっかり理解できて、愛犬に合った量を見つける第一歩が踏み出せるはずですよ。
公式サイトの給餌量ガイドの見方と計算方法
カナガンドッグフードの給餌量を決める上で、最も信頼できる情報源は公式サイトや商品パッケージに記載されている「給餌量ガイド」です。
こういったガイドを見ると、数字がたくさん並んでいて少し難しく感じるかもしれませんね。
でも、安心してください。
見るべきポイントさえ押さえれば、誰でも簡単です。
まず大切なのは、ガイドに書かれている数字が「1日あたり」の給餌量の目安であるということです。
これを1日2回に分けて与えるなら、単純に記載の量を半分にして、朝と晩に与える、という考え方になります。
特別な計算式を使う必要はなく、後ほど説明する「体重」「ライフステージ」「活動量」の3つの情報をもとに、ガイドの表に当てはめていくだけで、愛犬の給餌量の目安がわかるようになっています。
まずはこの「公式のガイドがすべての基本になる」という点を覚えておきましょう。
給餌量の計算に欠かせない3つのチェックポイント
公式サイトの給餌量ガイドを正しく使うためには、事前に愛犬の情報をいくつか確認しておく必要があります。
人間でも、年齢や体格、ライフスタイルによって食べる量が変わるのと同じで、ワンちゃんも一頭一頭個性がありますからね。
その個性を把握するための指標が、「体重」「ライフステージ」「活動量」の3つです。
なぜこの3つが重要かというと、ワンちゃんが1日に必要とするエネルギー量が、これらの要素によって大きく変わってくるからです。
例えば、育ち盛りの子犬と、のんびり過ごすシニア犬とでは、必要なカロリーが全く違います。
この3つのポイントをしっかり把握しておくことが、愛犬にとっての「適量」を見つけるための、とても大切な準備になるんですよ。
チェック1:愛犬の現在の体重
給餌量を決める上で、最も基本となる情報が「体重」です。
カナガンの給餌量ガイドも、体重別に目安量が記載されています。
「うちの子、だいたい〇〇kgくらいかな?」と曖昧に覚えている方もいるかもしれませんが、できれば正確な体重を把握しておくのが理想ですね。
特に子犬やシニア犬は体重が変化しやすいので、月に1回など、定期的に測ってあげることをおすすめします。
動物病院で測ってもらうのが一番正確ですが、自宅で測る場合は、まず飼い主さんがワンちゃんを抱っこして体重計に乗り、次に飼い主さんだけが乗ってその差を計算する方法が簡単です。
このひと手間が、愛犬の健康管理に繋がりますし、フードを与えすぎたり、逆に少なすぎたりするのを防ぐことにも繋がるんです。
チェック2:愛犬のライフステージ(子犬・成犬・シニア)
次に大切なのが、愛犬が今どのライフステージにいるか、ということです。
具体的には、「子犬」「成犬」「シニア(老犬)」の3つに分けられます。
子犬の時期は、体を作るためにたくさんのエネルギーと栄養を必要とします。
そのため、体重が同じ成犬と比べても、より多くのフード量が必要になることが多いです。
一方、シニア期に入ると基礎代謝や運動量が落ちてくるため、成犬期と同じ量を与えていると太りやすくなってしまうこともあります。
カナガンは全年齢に対応しているフードですが、それぞれのライフステージの特性を理解して給餌量を調整してあげることが、愛犬の生涯にわたる健康をサポートする上で非常に重要になってくる、というわけですね。
チェック3:愛犬の活動量(アクティブか、インドアか)
3つ目のチェックポイントは、愛犬の「活動量」です。
これは、毎日どれくらい運動しているか、ということですね。
例えば、同じ体重10kgの成犬でも、毎日ドッグランを走り回るのが大好きな活発な子と、お家でのんびり過ごすのが好きなインドア派の子とでは、1日に消費するカロリーが全く違います。
当然、消費カロリーが多い子の方が、たくさんのエネルギーを食事から補給する必要があります。
カナガンの給餌量ガイドにも、活動量が少ない犬向けと、活動量が多い犬向けの目安が書かれている場合があります。
「うちの子はどっちかな?」と、普段の愛犬の様子を思い浮かべながら、客観的に判断してあげることが大切です。
この活動量の見極めが、愛犬を肥満からも栄養不足からも守る鍵となります。
カナガンはなぜ少量でも栄養満点なの?その理由を解説
カナガンの給餌量ガイドを初めて見た方の中には、「あれ、思ったより与える量が少ないかも?」と感じる方もいるかもしれません。
実際に、今まで安価なドッグフードを与えていた場合、同じ感覚で量を測ると、カナガンは少なく見えることがあるんです。
その理由は、カナガンが非常に高栄養で、消化吸収に優れたレシピで作られているからなんですね。
主原料には上質なチキンやサーモンといった動物性タンパク質がたっぷり使われており、犬が本来必要とする栄養を効率よく摂取できます。
また、多くのドッグフードでかさ増しとして使われがちな、犬が消化を苦手とするトウモロコシや小麦などの「穀物」を一切使用しないグレインフリーなのも大きな特徴です。
つまり、中身がぎっしりと詰まっているイメージですね。
だから、少量に見えても、愛犬の健康維持に必要な栄養素をしっかりと補給できるというわけです。
【体重別】カナガンの給餌量目安表
それでは、具体的にどれくらいの量を与えればいいのか、公式サイトの情報を参考に「成犬(1歳以上)」の場合の給餌量目安を表にまとめてみました。
ご自身の愛犬の体重と照らし合わせて、1日の給餌量の参考にしてみてください。
| 犬の体重 | 1日の給餌量(活動量少なめ) | 1日の給餌量(活動量多め) |
|---|---|---|
| 1-5kg | 25-85g | 30-95g |
| 5-10kg | 85-145g | 95-160g |
| 10-20kg | 145-240g | 160-270g |
| 20-30kg | 240-325g | 270-365g |
| 30kg以上 | 325g以上 | 365g以上 |
ワンちゃんの種類、年齢、運動量、体質などによって最適な量は異なります。
特に最初のうちは、この目安量を基準にしながら、愛犬の便の状態や体重の増減をよく観察して、少しずつ調整していくことが何よりも大切ですよ。
初めて与えるなら「移行期間」の給餌量を守ろう
「カナガンに切り替えよう!」と決めた時、すぐにでも新しいフードをあげたくなる気持ちはよくわかります。
でも、ここはぐっとこらえて、ゆっくりと切り替えてあげてください。
いきなりフードを100%変えてしまうと、ワンちゃんの胃腸がびっくりしてしまい、下痢や軟便の原因になることがあるんです。
特にカナガンは栄養価が高いフードなので、慣れるまでは少し慎重になるのがおすすめです。
具体的には、1週間から10日ほどの「移行期間」を設けます。
最初の1〜2日は、今までのフードにカナガンを25%だけ混ぜて与えます。
問題がなければ、次の2〜3日は50%に、その次の2〜3日は75%に、といった具合に、徐々にカナガンの割合を増やしていくのが理想的な方法です。
この丁寧なステップが、愛犬のお腹の健康を守り、スムーズに新しい食事に慣れてもらうための秘訣です。
【ライフステージ別】カナガンの給餌量|子犬・成犬・シニア

ワンちゃんも私たち人間と同じで、年齢によって必要な食事の量や栄養バランスが変わってきますよね。
やんちゃで育ち盛りの「子犬期」、活動的で体が安定している「成犬期」、そして少しずつ穏やかになってくる「シニア期」。
それぞれのステージで、給餌量の考え方には少しずつ違ったポイントがあります。
カナガンは全犬種・オールステージ対応のドッグフードですが、だからこそ、飼い主さんが愛犬のライフステージに合わせて量を調整してあげることが、健康を長くサポートする秘訣になります。
ここでは、それぞれの時期に合わせた給餌量の考え方と、具体的な注意点について詳しく見ていきましょう。
【子犬期】成長を支える給餌量のポイント
子犬をお迎えした時の、あのワクワクする気持ちは特別なものですよね。
この時期は、これから先の犬生を支えるための体づくりをする、非常に大切な期間です。
骨格や筋肉、内臓などが急速に発達するため、成犬の比ではないくらいたくさんのエネルギーと栄養を必要とします。
カナガンは、主原料に良質なチキンをたっぷり使った高タンパクなフードなので、子犬の力強い成長をしっかりとサポートしてくれますよ。
ただし、子犬はまだ体が小さく、消化器官も未発達です。
一度にたくさんの量を食べることができないので、「1日に必要な量を、何回かに分けて与える」というのが基本中の基本になります。
焦らず、愛犬のペースに合わせて食事のリズムを作ってあげましょう。
月齢別の給餌回数と量の目安
子犬の食事でまず悩むのが、「1日に何回、ごはんをあげればいいの?」ということではないでしょうか。
消化能力が低い子犬は、一度にたくさんのフードを食べるとお腹を壊してしまうことがあるため、1日の給餌量をこまめに分けて与える必要があります。
あくまで一般的な目安ですが、月齢に合わせて以下のように回数を調整していくのがおすすめです。
・生後3ヶ月頃まで:1日4〜5回
・生後6ヶ月頃まで:1日3回
・生後10ヶ月〜1歳頃まで:1日2回
量については、成犬よりも体重あたりの要求エネルギー量が多いため、給餌量ガイドでも「子犬」の欄を見るようにしてください。
成犬用と同じ感覚で与えると、成長に必要な栄養が足りなくなってしまう可能性があります。
子犬は日々成長していくので、こまめに体重を測り、それに合わせてフードの量を少しずつ増やしていくことが大切です。
ドッグフードをふやかす場合の注意点
まだ乳歯が生えそろっていなかったり、ドライフードを上手に噛み砕けなかったりする子犬には、ぬるま湯でフードをふやかして与えるのがおすすめです。
ふやかすことには、消化器官への負担を減らすだけでなく、フードの香りがより強く立つことでワンちゃんの食欲を刺激するというメリットもあります。
ただし、いくつか注意点があります。
まず、フードの栄養素が壊れてしまう可能性があるため、熱湯を使うのは避けてください。
人肌くらいのぬるま湯で、10〜15分ほど置けば十分に柔らかくなります。
また、ふやかしたフードは傷みやすいので、作ったまま放置するのは絶対にやめましょう。
食べ残しは、もったいなく感じてもすぐに片付けるのが衛生的です。
水分を吸ってカサが増えるので、ワンちゃんがすぐにお腹いっぱいになってしまい、必要なカロリーを摂取できない場合もあるため、量の調整にも少し気を配ってあげてくださいね。
【成犬期】健康維持のための給餌量の調整方法
1歳を過ぎて成犬期に入ると、子犬の頃のような急激な成長は落ち着き、体格が安定してきます。
毎日のお散歩や遊びが一番楽しい、最も活動的な時期かもしれませんね。
この成犬期の食事管理が、シニア期以降の健康寿命に大きく影響してくると言われています。
つまり、今の食生活が将来の健康への投資になる、ということです。
給餌量の基本は、これまで通り公式サイトのガイドを参考にしつつ、「適正体重を維持すること」を目標に微調整を行っていきます。
ワンちゃんの体を触ってみて、肋骨がうっすらと感じられるくらいが理想的な体型です。
「最近ちょっと太ってきたかな?」「逆に痩せてきたかも?」と感じたら、それはフードの量を見直すサインかもしれません。
活動量(インドア派・アウトドア派)に合わせた調整
成犬期の給餌量調整で特に重要になるのが、愛犬の「活動量」を正しく見極めることです。
例えば、毎日のお散歩は30分程度で、あとは家でゆっくり過ごすのが好きなインドア派のワンちゃんと、毎週末ドッグランで思いっきり走り回ったり、飼い主さんと一緒にアウトドアを楽しんだりするのが日課のアクティブなワンちゃんとでは、1日に必要なエネルギー量が大きく異なります。
給餌量ガイドにある「活動量が少ない場合」「活動量が多い場合」のどちらを参考にするかは、飼い主さんが愛犬のライフスタイルを客観的に見て判断してあげる必要があります。
また、季節によっても活動量は変わります。
暑い夏は少し食欲が落ちたり、涼しい秋冬は活発になったりすることもあるので、そうした変化にも気づいてあげられると、より細やかな健康管理ができますね。
避妊・去勢手術後の給餌量について
多くのワンちゃんが成犬期に経験するのが、避妊・去勢手術です。
この手術後は、ホルモンバランスが変化することで、一般的に基礎代謝が落ち、太りやすくなる傾向があると言われています。
今までと同じ量のフードを与えているのに、なぜか体重が増えてきてしまう…というのは、多くの飼い主さんが経験することです。
そのため、手術を終えたら、食事の量を見直す良い機会だと考えてみてください。
獣医師さんと相談するのが一番ですが、一般的には、それまで与えていた量よりも1割〜2割程度減らすことが推奨されています。
カナガンのような栄養価の高いフードは、特に量の調整が体重に反映されやすいです。
手術後は、これまで以上に体重の増減を注意深くチェックして、愛犬が健康的な体型を維持できるようサポートしてあげましょう。
【シニア期(老犬)】消化に配慮した給餌量の考え方
犬種にもよりますが、だいたい7歳頃からがシニア期(老犬)の入り口と言われています。
若い頃のように走り回ることは減り、寝ている時間が増えるなど、少しずつ体に変化が見られるようになります。
外見だけでなく、体内でも基礎代謝や消化機能が穏やかに低下してくる時期です。
そのため、成犬期と同じ量の食事を与えていると、消費エネルギーが追いつかずに肥満になってしまうことがあります。
肥満は足腰の関節や心臓などの内臓に負担をかけてしまうため、シニア期こそ体重管理が重要になります。
食事の「量」を少しずつ減らしていくことを意識しつつ、消化が良く、質の高い栄養を摂れるように考えてあげたいですね。
カナガンは、消化の負担になる穀物を使わないグレインフリーなので、その点でもシニア犬に優しいフードだと言えるかもしれません。
運動量が減ってきた場合の調整方法
「最近、お散歩に行ってもすぐに帰りたがるようになった」「大好きだったおもちゃで遊ぶ時間が短くなった」こんな様子が見られたら、それは運動量が減ってきたサインです。
消費するエネルギーが減っているのですから、食事から摂取するエネルギーも合わせて調整してあげる必要があります。
具体的な調整方法としては、まず成犬期に与えていた量から10%〜20%ほど減らすことを目安にしてみてください。
ただし、急にガクッと減らすのはやめましょう。
愛犬の体重や体型(背中を触って、背骨や肋骨がゴツゴツしすぎていないかを確認する「ボディコンディションスコア」が参考になります)をこまめにチェックしながら、1〜2週間かけてゆっくりと新しい量に慣らしていくのが理想です。
少しの変化に気づいてあげることが、シニア期の愛犬の快適な生活に繋がります。
シニア犬が食べやすい与え方の工夫
年齢を重ねると、歯が弱くなったり、噛む力や飲み込む力が衰えてきたりすることもあります。
ドライフードを硬そうに食べていたり、食べこぼしが増えたりした場合は、少し工夫をしてあげると良いでしょう。
一番簡単な方法は、子犬の時と同じように、フードをぬるま湯で少しふやかしてあげることです。
こうすることで、フードが柔らかくなり食べやすくなるのはもちろん、消化の助けにもなります。
また、香りが強く立つので、嗅覚が衰えて食欲が落ち気味なシニア犬の食欲を刺激する効果も期待できます。
一度に食べられる量が減ってきたと感じるなら、1日の給餌量は変えずに、食事の回数を2回から3回に増やしてあげるのも良い方法です。
一度の食事量を減らすことで、胃腸への負担を軽くすることができますよ。
カナガンの給餌量でよくある間違いと注意点
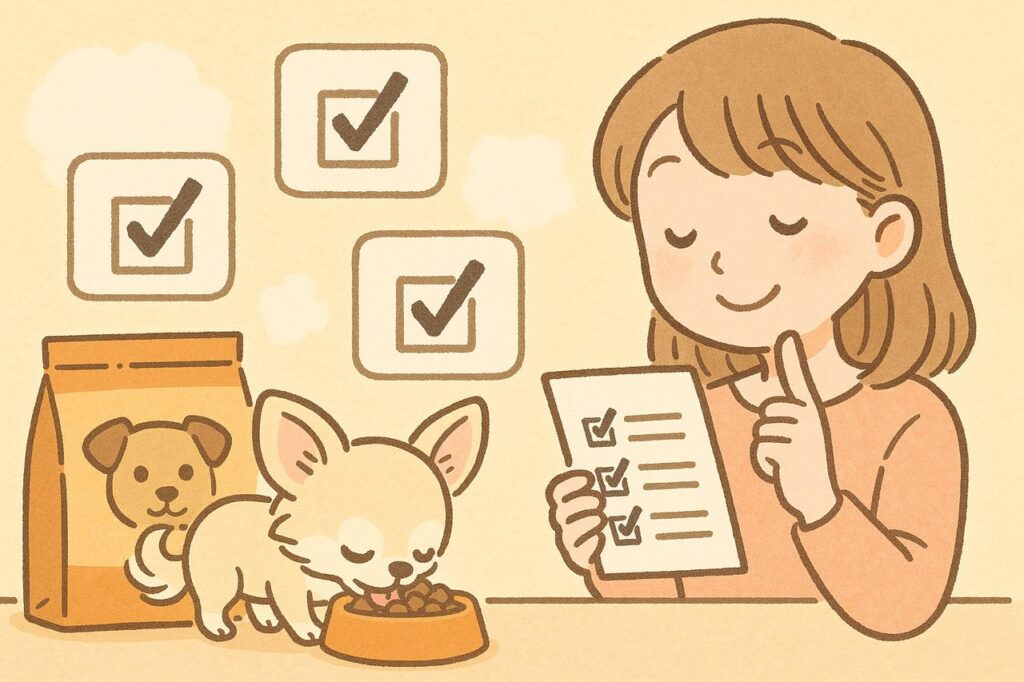
愛犬のライフステージに合わせた給餌量の基本がわかっても、毎日のこととなると「これで本当に大丈夫かな?」と不安になる瞬間ってありませんか?
良かれと思ってやっていたことが、実はちょっとした間違いだった、なんてことも意外とあるものです。
僕自身も、愛犬の「もっとちょうだい!」という可愛い顔に負けて、ついつい量を増やしてしまいそうになることがあります。
ここでは、そんな飼い主さんが陥りがちな給餌量の失敗例や、ぜひ知っておいてほしい注意点を具体的に解説していきます。
ここを読めば、日々のフード管理に対する自信がついて、もっと安心して愛犬との食事の時間を楽しめるようになりますよ。
与えすぎが招くリスクとは?肥満は万病のもと
愛犬がおいしそうにごはんを食べてくれる姿は、飼い主にとって何よりの幸せですよね。
その喜ぶ顔が見たくて、ついついお皿にフードを多めに入れてしまったり、おかわりをあげてしまったり…。
その気持ち、痛いほどよくわかります。
ですが、その愛情が、長い目で見ると愛犬の健康を損なう原因になってしまう可能性もあるんです。
一般的に、犬の肥満は関節への負担を増やしたり、心臓や呼吸器系の病気、糖尿病などのリスクを高めたりすると言われています。
特にカナガンは、少量でも必要な栄養がしっかりとれる高栄養なフードです。
つまり、ほんの少しの「あげすぎ」が、気づかないうちにカロリーオーバーに繋がりやすい、という側面もあります。
愛犬に一日でも長く健康でいてもらうために、心を鬼にして「適量」を守ることも、飼い主の大切な愛情表現の一つなのかもしれませんね。
「足りないかも?」給餌量が少ない場合のサインを見逃さないで
肥満のリスクを意識するあまり、今度は逆に「もしかして、与える量が少なすぎる…?」と心配になってしまう飼い主さんもいます。
特に、活発に運動する子や、代謝が良い若い犬の場合、ガイド通りの量では少し足りないというケースも実際にあります。
では、給餌量が足りているかどうかは、どこで判断すれば良いのでしょうか。
一番わかりやすいのは、体重の変化です。
適正だった体重が徐々に減ってきている場合は、栄養が足りていない可能性があります。
また、体を触ってみて、あばら骨や腰骨がゴツゴツと浮き出てわかるようなら、痩せすぎのサインです。
他にも、毛のツヤがなくなってきたり、以前よりも元気がなくぐったりしている時間が増えたり、といった変化に現れることもあります。
食後にいつまでもお皿を舐め続けているのも、「まだ食べたいよー!」という愛犬からのメッセージかもしれません。
こうしたサインを見逃さず、必要に応じて少し量を増やして様子を見てあげましょう。
おやつをあげる時の給餌量の調整ルール
しつけのご褒美や、コミュニケーションの一環として、おやつは欠かせない存在ですよね。
あの嬉しそうな顔を見ると、こちらも幸せな気分になります。
ただし、忘れてはいけないのが、おやつのカロリーです。
人間が食事の他に、ついついお菓子をつまんでしまうのと同じで、おやつのカロリーも1日の総摂取カロリーにきちんと含めて考える必要があります。
一般的には、「おやつのカロリーは、1日に必要な総カロリーの10%以内」に抑えるのが理想的とされています。
つまり、おやつをあげた日は、そのカロリー分、主食であるカナガンの量を減らしてあげるのが正解です。
例えば、歯磨きガムを1本あげたら、いつものフードをスプーン1杯分減らす、といった具合です。
毎回厳密にカロリー計算をするのは大変ですが、「おやつは食事の一部」という意識を持って、あげすぎないように気をつけるだけでも、愛犬の体重管理は大きく変わってきますよ。
フードを切り替える際の正しい手順と量の調整
新しいフードに切り替える時は、1週間ほどかけてゆっくり慣らす「移行期間」が大切だ、というお話は先にしましたね。
ここでは、その移行期間中によくある「量」の間違いについてお話しします。
それは、「新しいフードを混ぜた分、全体の量が増えてしまう」というケースです。
例えば、いつも100gのフードをあげている子がいたとします。
切り替え初日、カナガンを25%混ぜる場合、正しくは「今までのフード75g + カナガン25g = 合計100g」としなければいけません。
これを、「今までのフード100g + カナガン25g」としてしまうと、その日は125gも食べさせることになり、完全なカロリーオーバーです。
これを1週間も続けてしまうと、お腹の調子を崩したり、体重増加の原因になったりします。
切り替え中は、あくまで「全体の食事量は変えずに、中身の割合だけを変えていく」ということを忘れないようにしてくださいね。
焦らず、愛犬のお腹の調子を最優先に進めていきましょう。
正確な計量が重要!計量カップよりスケールがおすすめな理由
毎日のフードの計量、あなたは何を使っていますか?
ドッグフードを購入した時についてくる計量カップを使っている、という方も多いかもしれません。
手軽で便利なのですが、実はこの計量カップでの計測には、一つ大きな落とし穴があります。
それは、「毎回正確な“重さ”を測るのが難しい」ということです。
ドライフードは、粒の大きさや密度が一定ではありません。
そのため、カップで「すりきり一杯」を計ったつもりでも、その時々で誤差が生まれ、実際には10gや20gも重さが違っている、なんてことが普通に起こります。
この毎日の小さな誤差が、積もり積もって体重の増減に繋がるのです。
そこでおすすめしたいのが、キッチン用の「デジタルスケール(はかり)」です。
これを使えば、毎日1g単位で正確に給餌量を管理できます。
最近では1,000円前後でも十分な性能のものが手に入ります。
愛犬の健康管理が格段にレベルアップすることを考えれば、決して高い投資ではないと思いますよ。
カナガンの給餌量に関するQ&A

さて、ここまでカナガンの給餌量について、基本的な考え方からライフステージ別の調整方法、注意点まで詳しく見てきました。
それでも、「こういう場合はどうしたらいいの?」といった、個別の細かい疑問はまだまだ残っているかもしれませんね。
僕も新しいドッグフードを試す時は、いつも細かいことが気になって色々と調べてしまいます。
ここでは、そんな飼い主さんの「あとちょっと知りたい!」という気持ちにお応えするために、特に多く寄せられる質問をQ&A形式でまとめてみました。
あなたの疑問も、きっとここで解決するはずですよ。
Q. カナガンを子犬に与える際の注意事項は?
はい、カナガンは全犬種・オールステージ対応なので、もちろん子犬にも安心して与えることができます。
ただし、いくつか注意していただきたい点があります。
まず一番大切なのが「給餌量」です。
子犬は体を大きく成長させるために、成犬の2倍近い栄養を必要とすることもあります。
必ずパッケージや公式サイトに記載されている「子犬用」の給餌量ガイドを参考にしてください。
次に「与え方」です。
子犬はまだ消化器官が未熟なので、1日の給餌量を3〜5回に分けて、少量ずつ与えるのが基本です。
必要に応じてぬるま湯でふやかしてあげると、消化の助けにもなり、食いつきも良くなるのでおすすめですよ。
そして最後に「切り替え」です。
他のフードからカナガンに切り替える際は、成犬以上に慎重に、最低でも10日以上かけるつもりで、ゆっくりと割合を増やしてあげてくださいね。
Q. カナガンを食べてくれない場合にはどうすれば?
愛犬が急にごはんを食べてくれないと、すごく心配になりますよね。
でも、まずは慌てずに、いくつか試せる方法があります。
一番手軽なのは、人肌程度のぬるま湯でフードを少しふやかしてみることです。
カナガン本来のチキンの香りがより強く引き立ち、ワンちゃんの食欲を刺激してくれることがあります。
また、食器の置いてある場所が騒がしくて落ち着かない、といった環境が原因の場合もありますので、静かな場所に移動してあげるのも一つの手です。
それでも食べない場合は、茹でたささみや野菜などを少量トッピングしてみるのも良いでしょう。
ただし、トッピングに慣れてしまうと、それがないと食べない子になる可能性もあるので、常用は慎重に考えた方が良いかもしれません。
もし、食欲がない状態が続き、嘔吐や下痢、ぐったりしているなど、他に気になる症状がある場合は、迷わず動物病院を受診してください。
Q. 1日の給餌回数は何回がベスト?
1日の給餌回数に「絶対にこれ!」という正解はありませんが、一般的には愛犬のライフステージに合わせて変えるのが良いとされています。
まず【子犬期】は、消化器官への負担を減らすために、1日の量を3〜5回に分けてこまめに与えるのが理想です。
次に【成犬期】は、健康な子であれば1日2回、朝と晩に与えているご家庭が最も多いです。
ただし、一度にたくさん食べると胃が拡張して捻転を起こす「胃捻転」のリスクが高い大型犬などは、1日3回に分けて1回の食事量を減らすこともあります。
そして【シニア期】は、再び消化機能が穏やかになってくるため、成犬期と同じ量でも1日3〜4回に分けてあげると、胃腸への負担を軽減できます。
愛犬の年齢や体調、生活リズムに合わせて、最適な回数を見つけてあげてください。
Q. 体重が増えてきた…どうやって量を調整する?
「最近なんだか愛犬が丸くなってきたかも…」と感じたら、食事の量を見直すサインです。
まず、おやつのあげすぎや運動不足など、食事以外の原因がないか生活習慣を振り返ってみましょう。
その上でフードの量を調整する場合は、いきなり大幅に減らすのではなく、今与えている量から5%〜10%程度減らすことから始めてみてください。
例えば、1日100gあげているなら、まずは90g〜95gにしてみる、といった具合です。
そして、その状態で1〜2週間ほど体重の推移を観察します。
急激なダイエットはワンちゃんの体にも負担をかけますし、ストレスの原因にもなります。
定期的に体重を測り、体を触って肋骨の感触を確かめる「ボディコンディションスコア」で体型をチェックしながら、焦らずゆっくりと適正体重を目指していくことが大切ですよ。
Q. 他のフードと混ぜて与えても大丈夫?
まず基本的な考え方として、カナガンはそれ単体で犬に必要な栄養素がバランス良く配合されている「総合栄養食」なので、他のフードを混ぜる必要はありません。
ただ、アレルギー対策や病気の治療などで獣医師から特定の療法食を与えるよう指導されている場合や、どうしても食いつきが悪い時の工夫として、他のフードと混ぜたいケースもあると思います。
その場合に最も注意すべきなのは「カロリーオーバー」です。
例えば、カナガンに他のフードを30g混ぜるのであれば、本来与えるはずだったカナガンの量から、混ぜたフードのカロリー分を差し引く必要があります。
また、栄養バランスが崩れてしまう可能性もゼロではありません。
もし他のフードと混ぜることを考えるのであれば、一度かかりつけの獣医師さんに相談してみるのが一番安心だと思います。
Q. カナガンの賞味期限、保存方法は?
ドッグフードの品質を保つ上で、賞味期限と保存方法はとても重要です。
カナガンの賞味期限は、未開封の状態で製造から18ヶ月です。
パッケージの裏面などに「BBD(Best Before Date)」として印字されているので確認してみてください。
そして、もっと大切なのが開封後の保存方法です。
開封した瞬間からフードは酸化が始まりますので、風味や品質を損なわないためにも、開封後は1ヶ月〜1ヶ月半くらいで使い切るのが理想です。
保存する際は、袋の中の空気をできるだけ抜いて、付属のジッパーをしっかりと閉め、高温多湿や直射日光が当たらない、涼しくて暗い場所に保管しましょう。
冷蔵庫での保管は、出し入れの際に生じる温度差で結露が発生し、カビの原因になることがあるので避けてください。
市販のフードストッカーなど、密閉性の高い容器に移し替えるのもおすすめですよ。
Q. カナガンにサンプルやお試しはある?
「いきなり2kgの袋を買うのはちょっと不安…」と感じる方もいらっしゃいますよね。
残念ながら、2025年現在、カナガンの公式サイトでは無料サンプルの配布は行っていないようです。
その代わりに、多くの方が利用しているのが「定期コース」です。
定期コースと聞くと「何度も買わないといけないの?」と身構えてしまうかもしれませんが、カナガンの定期コースはいつでも解約や休止が可能です。
つまり、初回は割引価格で購入してみて、もし愛犬に合わないと感じたら、次回のお届け前にマイページなどから簡単に解約手続きができる、ということです。
「1回だけお得に試せる」という感覚で利用できるので、初めての方でも安心して始められるシステムになっているんですね。
Q. カナガンの会員ログインの方法と会員ページでできることは?
カナガンを公式サイトで購入すると、自動的に会員登録され、専用の「マイページ」が使えるようになります。
公式サイトの上部にあるログインボタンから、登録したメールアドレスとパスワードで簡単にログインできますよ。
このマイページが、実はとても便利なんです。
例えば、以下のような手続きが電話をしなくても24時間いつでもウェブ上で行えます。
・定期コースのお届け周期の変更(「4週間ごと」を「6週間ごと」にするなど)
・次回お届け予定日の変更
・お届け個数の変更
・定期コースの休止・再開
・登録住所やクレジットカード情報の変更
愛犬の食べるペースに合わせてフードの量を調整したら、それに合わせてお届けの周期をマイページでサッと変更できるので、フードが余ったり足りなくなったりする心配がありません。
まとめ:愛犬に合ったカナガンの適量を見つけて健康な毎日を
たくさんの情報があったので、少し難しく感じられた部分もあったかもしれませんね。
でも、一番大切なことは実はとてもシンプルです。
それは、「ガイドの量を基本にしながら、目の前にいる愛犬の様子をしっかりと観察してあげること」に尽きます。
記事のポイントを簡単におさらいしましょう。
・給餌量の基本は公式サイトのガイドを見ること
・「体重」「ライフステージ」「活動量」の3つが量を決める鍵
・子犬、成犬、シニアの各ステージに合わせた調整を忘れないこと
・おやつのカロリーも考慮し、できればスケールで正確に計量すること
これらのポイントを押さえつつ、日々の愛犬のうんちの状態や体重の変化、毛ヅヤの良し悪しなどをチェックしてあげてください。
ぜひ、あなたの愛犬に合った適量を見つけて、一日でも長く、元気いっぱいの楽しい毎日を一緒に過ごしてくださいね。
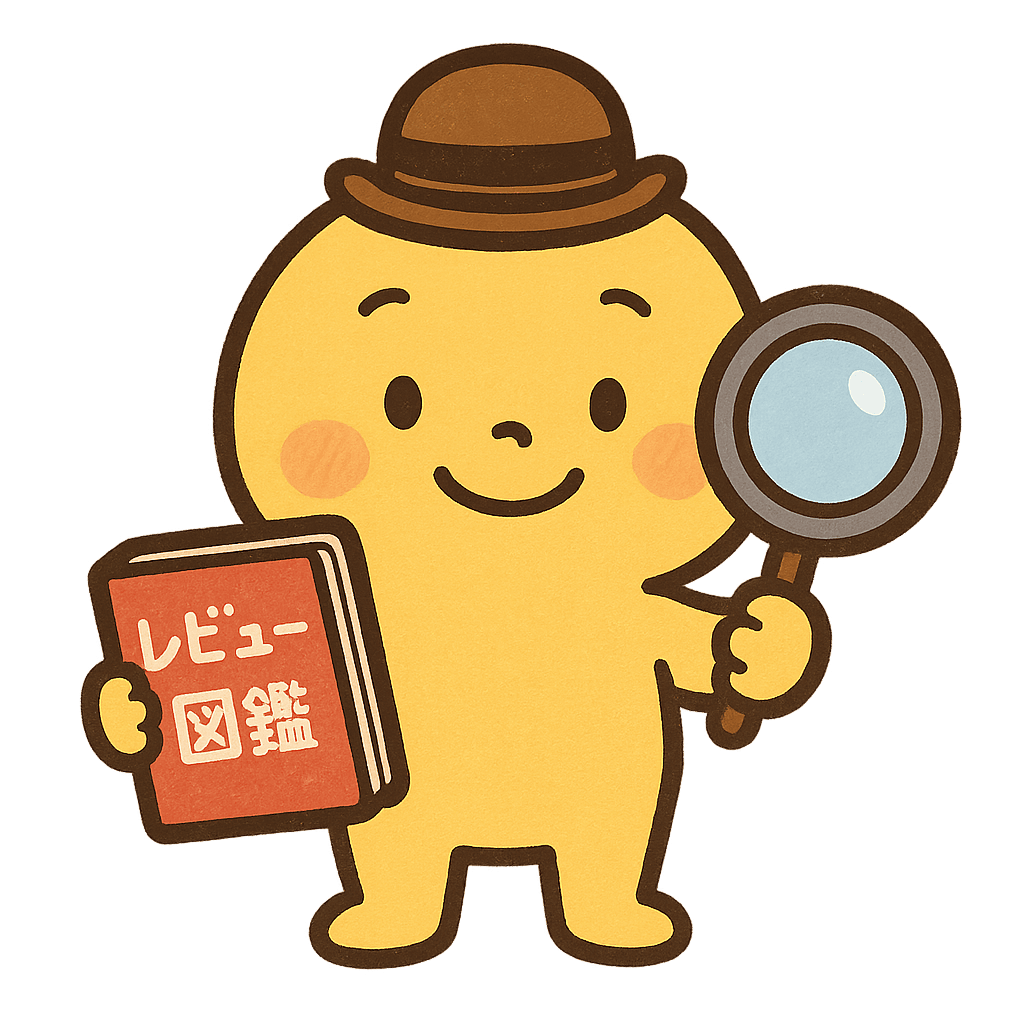
食事管理は、つい目分量で済ませてしまいがちな私…。
毎日のことですが、ほんの数グラムの違いを意識するだけで、愛犬の体調や未来の健康と真剣に向き合える気がします。
結局のところ、どんなに優れたガイドラインがあっても、日々の愛犬の小さな変化に気づいてあげられる「飼い主の観察眼」こそが、最高のレシピなのかもしれませんね。