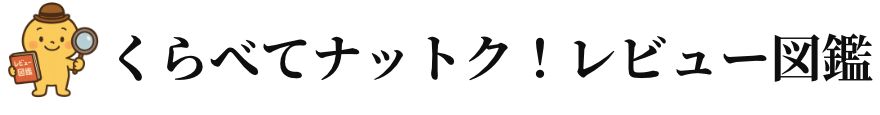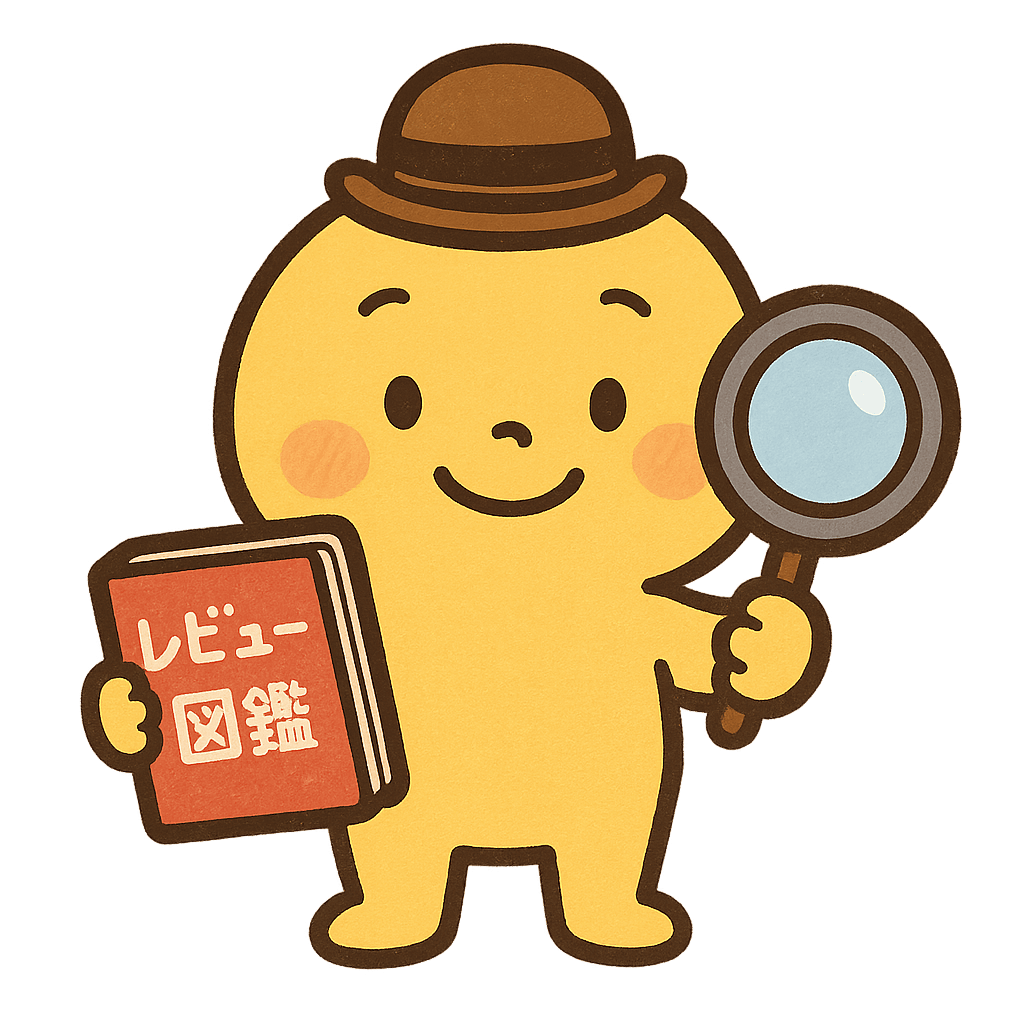
「ベッドフレームを置かずに、マットレスを床に直接置いて広々とした寝室にしたいな」。
そう考えて、人気のネルマットレスを検討している方も多いのではないでしょうか。
お部屋がスッキリするし、初期費用も抑えられるし、良いことづくめに見えますよね。
でも、心のどこかで「床に直置きって、湿気やカビは大丈夫なのかな…?」「せっかく買ったマットレスがすぐにダメになったらどうしよう」と、一抹の不安がよぎっていませんか。
この記事では、そんなあなたの不安をスッキリ解消するために、ネルマットレスを直置きする際の注意点をわかりやすく解説していきます。
ネルマットレスの直置きは「対策すれば」OK!
「ネルマットレスって、ベッドフレームなしで床に直接置いて使ってもいいのかな?」。
そんな風に考えている方も多いのではないでしょうか。
お部屋を広く見せたい、初期費用を抑えたい、シンプルな暮らしがしたい、など理由は様々だと思います。
先に結論からお伝えすると、ネルマットレスの直置きは「正しい湿気・カビ対策」をすれば全く問題ありません。
むしろ、ベッドフレームがない生活のメリットを享受しながら、最高の寝心地を手に入れることができます。
ただ、何も考えずにそのままポンと床に置いてしまうと、後で「しまった…」と後悔する可能性があるのも事実です。
マットレスにとって最大の敵である「湿気」が、床との間にこもってしまい、カビや劣化の原因になってしまうからですね。
ここでは、そんな不安を解消するために、ネルマットレスを直置きする場合のデメリットと、それを回避するための具体的な対策を徹底的に解説していきます。
この記事を読み終える頃には、「なるほど、こうすればいいのか!」とスッキリした気持ちで、安心してネルマットレスを直置きできるようになっているはずですよ。
まずは結論から!条件付きで直置きは可能です
改めまして、ネルマットレスは床に直置きして使うことができます。
ただし、これには「適切な湿気対策を行う」という大切な条件がつきます。
ネルマットレス自体は、一般的なウレタンマットレスと比較して通気性が非常に高い構造になっています。
それでも、私たちが寝ている間にかく汗の量は、想像以上です。
一晩でコップ一杯分とも言われる汗は、マットレスを通して下へ下へと抜けていきます。
ベッドフレームがあれば、その下は空間なので湿気は自然と逃げていきますが、床に直置きしていると、湿気の逃げ場がなくなってしまうんですよね。
特に、日本は湿度の高い気候です。
梅雨の時期や夏場はもちろん、冬でも窓の結露など、一年を通して湿気対策は欠かせません。
ですので、「ネルマットレスは通気性が良いから大丈夫」と過信するのではなく、「通気性が良いネルマットレスだからこそ、しっかり対策すれば鬼に金棒」という考え方で、賢く直置きを活用していくのが正解だと思います。
そのための具体的な方法は、この後じっくり解説していきますね。
なぜ「対策なし」の直置きは推奨されないのか?
では、なぜ「対策なし」での直置きは、どのマットレスメーカーも推奨していないのでしょうか。
その最大の理由は、やはり「カビのリスク」です。
先ほども少し触れましたが、床とマットレスの間は、湿気と人の体温によって、カビが繁殖するのに最適な環境が整ってしまいます。
カビは、一度発生してしまうと完全に取り除くのが非常に困難です。
見た目が悪いのはもちろんですが、胞子を吸い込むことでアレルギーや喘息といった健康被害を引き起こす可能性も指摘されています。
せっかく睡眠の質を高めるために奮発して買ったマットレスが、健康を害する原因になってしまったら、元も子もありませんよね。
また、湿気はカビだけでなく、マットレス内部のコイルを錆びさせたり、ウレタンを劣化させたりと、マットレスそのものの寿命を縮める原因にもなります。
ネルマットレスには10年間の耐久保証がついていますが、それは適切なお手入れをしていることが前提です。
「知らなかった」では済まされない事態を避けるためにも、対策なしの直置きは絶対に避けるべき、というのが私の考えです。
ベッドフレームがない暮らしのメリットとは
ここまで少し脅かすような話をしてしまいましたが、もちろん直置きにはたくさんのメリットがあります。
だからこそ、多くの方が直置きを検討しているわけですよね。
例えば、一番大きいのはお部屋の圧迫感がなくなり、広くスッキリ見えることではないでしょうか。
ベッドという大きな家具がなくなるだけで、視線が抜けて天井が高く感じられ、開放的な空間を演出できます。
お子様が小さいご家庭では、ベッドからの転落の心配がないのも大きな安心材料です。
また、ベッドフレームを購入する費用がかからないので、その分マットレス本体や他の寝具にお金をかけることができます。
お掃除の面でもメリットはあります。
ベッド下はホコリが溜まりやすいですが、マットレスをサッと立てかければ、いつでも気軽に掃除機をかけることができますよね。
こうしたメリットを最大限に活かしつつ、先ほど挙げたようなデメリットをしっかり対策で潰していく。
それが、ネルマットレスで快適な直置きライフを送るための鍵となるわけです。
この記事を読めば、直置きの不安がスッキリ解消されます
ここまで読んでいただいて、「やっぱり対策は大事なんだな」と感じていただけたかと思います。
でも、具体的に何をどうすれば良いのか、まだ分からないことだらけで不安ですよね。
ご安心ください。
ここでは、ネルマットレスを床に直置きする際に考えられるデメリットを一つずつ挙げ、そのすべてに対する具体的な解決策を、誰にでも分かりやすく解説していきます。
例えば、以下のような内容です。
・直置きすることで発生する5つの具体的なデメリット
・今日からすぐに実践できる、湿気とカビの完全対策ガイド
・そもそも、なぜネルマットレスが通気性に優れているのかという構造の秘密
・直置きに関する、よくある疑問とその回答
これらを順番に読み進めていただくことで、あなたの疑問や不安はすべて解消されるはずです。
そして、自信を持って「我が家はネルマットレスを直置きで使っています!」と言えるようになりますよ。
それでは、一緒に見ていきましょう。
ネルマットレスの基本情報をおさらい
本題に入る前に、まずはネルマットレスの基本的な情報について、簡単におさらいしておきましょう。
すでに購入済みの方は、読み飛ばしていただいても大丈夫です。
ネルマットレスは、寝返りのしやすさに特化して作られた、今とても人気のあるマットレスです。
サイズ展開も豊富で、一人暮らしの方から家族で使えるキングサイズまで揃っています。
特に注目したいのが、120日間のフリートライアルと、10年間の耐久保証です。
マットレスのような高価な買い物で失敗したくない、という方にとって、これは非常に心強いサービスですよね。
自宅でじっくりと寝心地を試せるので、自分に合うかどうかを納得した上で判断することができます。
以下に、サイズごとの詳細なスペックをまとめましたので、参考にしてみてください。
| サイズ | 寸法(cm) | 重量(kg) | コイル数 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| シングル | 95 × 195 × 21 | 22.0 | 1,173個 | ¥79,900 |
| セミダブル | 120 × 195 × 21 | 26.2 | 1,479個 | ¥94,900 |
| ダブル | 140 × 195 × 21 | 31.2 | 1,734個 | ¥109,900 |
| クイーン | 160 × 195 × 21 | 35.3 | 1,989個 | ¥134,900 |
| キング | 190 × 195 × 21 | 41.9 | 2,397個 | ¥154,900 |
要注意!ネルマットレスを床に直置きする5つのデメリット

前の章で「対策をすれば直置きはOK」とお伝えしましたが、逆に言えば、対策をしないと様々なデメリットが発生する可能性があります。
「まあ大丈夫だろう」と油断していると、せっかくのネルマットレスの性能を最大限に引き出せないばかりか、後悔することにもなりかねません。
ここでは、ネルマットレスを床に直置きすることで起こりうる5つの代表的なデメリットを、一つずつ詳しく見ていきましょう。
これらを知っておくことで、次にご紹介する「対策」の重要性が、より深くご理解いただけるはずです。
なぜ対策が必要なのか、その理由をしっかりと頭に入れておきましょう。
デメリット①:湿気がこもりカビが発生しやすくなる
まず、最も警戒すべきデメリットが、湿気によるカビの発生です。
これはネルマットレスに限らず、すべてのマットレスに共通して言える最大のリスクだと思います。
「新しいマットレスなのに、いつの間にか裏側に黒い点々が…」なんてことになったら、本当にショックですよね。
カビは見た目の不快感だけでなく、アレルギー性鼻炎や気管支喘息など、健康に直接的な悪影響を及ぼすこともあります。
特に小さなお子様やアレルギー体質の方がいるご家庭では、細心の注意が必要です。
では、なぜ直置きするとカビが発生しやすくなるのでしょうか。
その主な原因は、「寝汗」と「結露」にあります。
寝汗による湿気が逃げられない
私たちは、季節に関係なく、寝ている間にたくさんの汗をかきます。
その量は、一晩で約200ml、コップ一杯分にもなると言われているんです。
自分ではそんなに汗をかいているつもりがなくても、体は常に水分を発散して体温を調節しています。
その汗や湿気は、パジャマやシーツを通り抜け、マットレス内部へと浸透していきます。
通気性の良いネルマットレスは、その湿気をうまく外部へ逃がす構造になっていますが、床に直接置かれていると、マットレスの底面から湿気が放出されるのを床が塞いでしまいます。
行き場を失った湿気はマットレスの底に溜まり続け、カビが繁殖するのに最適なジメジメした環境を作り出してしまう、というわけです。
床とマットレスの温度差で結露が発生
もう一つの原因が、特に冬場に起こりやすい「結露」です。
寒い日に、窓ガラスに水滴がたくさんつく、あの現象と同じですね。
私たちの体温によって温められたマットレスの内部と、暖房が効いていない冷たい床との間には、大きな温度差が生まれます。
これにより、マットレスの底面や床との接地面で空気が冷やされ、空気中の水分が水滴となって現れるのです。
寝汗をかいていないつもりでも、マットレスの裏側がびっしょり濡れていた、というケースは少なくありません。
この結露による水分も、カビの大きな原因となります。
特に気密性の高いマンションなどでは、冬場の結露対策は必須と言えるでしょう。
デメリット②:ホコリやハウスダストを吸い込みやすい
衛生面でのデメリットも無視できません。
実は、床から30cmまでの空間は、ホコリやダニの死骸、花粉といったハウスダストが最も浮遊しやすい「ハウスダストゾーン」と呼ばれています。
人が室内を歩くだけで、床に積もっていたホコリは簡単に舞い上がりますが、重さがあるため、すぐにまた床近くに落ちてくるのです。
床に直接マットレスを敷いて寝るということは、まさにこのハウスダストゾーンに顔を近づけて一晩中呼吸をし続ける、ということになります。
日中は気にならなくても、睡眠中、無意識のうちに大量のハウスダストを吸い込んでしまう可能性があるわけです。
これは、アレルギー症状の悪化につながることもありますし、今はアレルギーがない人でも、将来的なリスクを高めることになりかねません。
デメリット③:冬場は床からの冷気で底冷えする
寝心地という観点からも、デメリットがあります。
それは、冬場の「底冷え」です。
特にフローリングの床は、冬になると驚くほど冷たくなりますよね。
ベッドフレームがあれば床との間に空気の層ができるため、冷気は直接伝わってきませんが、直置きの場合は床の冷たさがダイレクトにマットレスに伝わります。
ネルマットレスは21cmの厚みがありますが、それでも長時間寝ていると、床からの冷気で背中がスースーしたり、寒くて夜中に目が覚めてしまったりすることがあります。
体が冷えると血行が悪くなり、睡眠の質も低下してしまいます。
せっかく寝心地の良いマットレスを選んだのに、寒さでぐっすり眠れないのでは意味がないですよね。
特に冷え性の方にとっては、これはかなり切実な問題だと思います。
デメリット④:マットレスの寿命を縮める可能性がある
見過ごされがちですが、マットレス自体の寿命にも影響を及ぼします。
先ほどから繰り返しお伝えしている「湿気」は、マットレスにとってまさに天敵です。
湿気はカビを発生させるだけでなく、マットレス内部の素材を劣化させる原因にもなります。
例えば、ネルマットレスの寝心地を支えているポケットコイルは金属製です。
湿気が多い環境に長期間さらされると、コイルが錆びてしまい、本来の弾力性や耐久性が損なわれる可能性があります。
また、クッション材として使われているウレタンフォームも、湿気によって「加水分解」という化学変化を起こし、ボロボロになってしまうことがあります。
ネルマットレスには10年間の長期保証がついていますが、それはあくまで適切な使用環境下での話です。
湿気対策を怠ったことが原因で劣化が進んだ場合、保証の対象外と判断される可能性もゼロではありません。
大切なマットレスを長く愛用するためにも、湿気対策は非常に重要です。
デメリット⑤:掃除がしにくく不衛生になりがち
最後のデメリットは、日常のメンテナンスに関するものです。
ベッドフレームを使っていれば、ベッド下の掃除は掃除機やフロアワイパーで比較的簡単に行えます。
しかし、マットレスを直置きしている場合、掃除をするためには毎回マットレスを動かさなければなりません。
ネルマットレスはシングルサイズでも約22kgあり、女性一人で毎日動かすのはかなりの重労働ですよね。
ついつい「今日はいいか…」と掃除を後回しにしてしまうこともあるのではないでしょうか。
その結果、マットレスの下にはホコリや髪の毛、フケなどが溜まり、それをエサにするダニが繁殖しやすい環境になってしまいます。
マットレスの裏側だけでなく、床も清潔に保つことが、快適な睡眠環境を維持する上ではとても大切です。
この「掃除のしにくさ」も、直置きの隠れたデメリットと言えるでしょう。
そもそもネルマットレスは通気性が高い!直置きでも安心な4つの理由
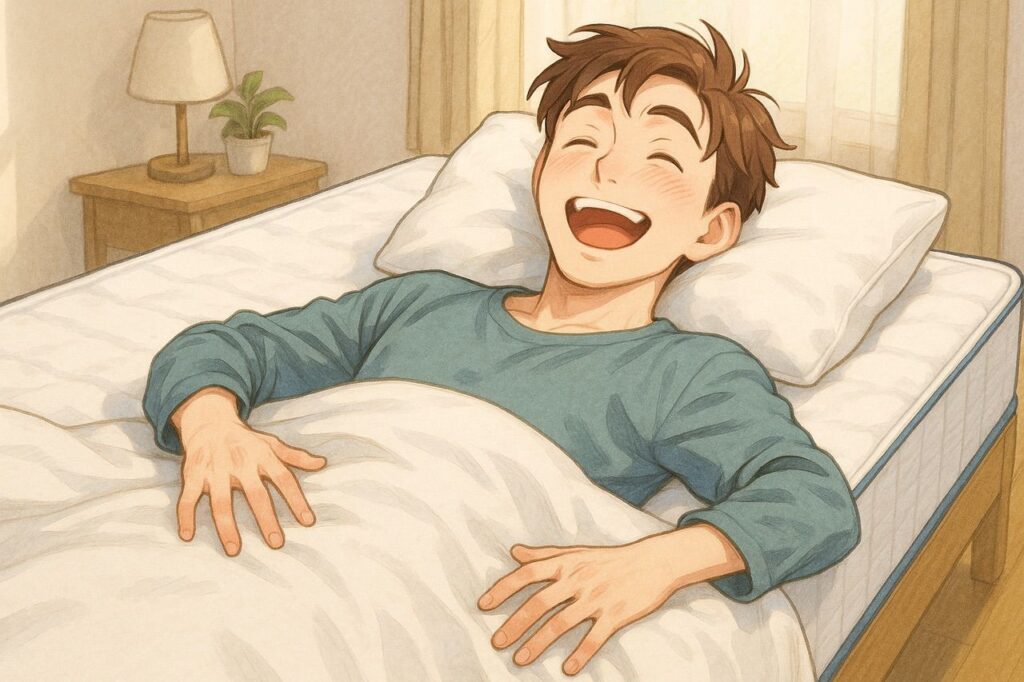
ここまで、直置きのデメリットと、それを防ぐための様々な対策についてお話ししてきました。
「なんだか、直置きって結構大変そう…」と感じた方もいるかもしれませんね。
でも、実はネルマットレスは、他の一般的なマットレスと比べて、もともと湿気やカビに強く、直置きでもある程度の安心感を持てる構造になっているんです。
もちろん、これまでお伝えしてきた対策が不要になるわけではありません。
しかし、「なぜネルマットレスが選ばれているのか」その理由を知ることで、「しっかり対策すれば、これほど心強いマットレスはないんだ」と、きっと納得していただけるはずです。
ここでは、ネルマットレスが持つ通気性の秘密と、直置きでも安心な4つの理由を詳しく解説します。
理由①:湿気を溜め込まない独自の13層構造
ネルマットレスの最大の特徴とも言えるのが、その独自の「13層構造」です。
実は、マットレスのカビやへたりの大きな原因となるのが、分厚いウレタン層なんです。
ウレタンは寝心地を調整するために多くのマットレスで使われていますが、一度湿気を吸い込むと、スポンジのように溜め込んでしまい、なかなか乾きにくいという性質があります。
そこでネルマットレスは、この分厚いウレタンを使わず、薄いウレタンと不織布を交互に何層にも重ねるという、非常にユニークな構造を採用しました。
この構造のおかげで、マットレスの内部にたくさんの空気の層が生まれ、まるで呼吸するように湿気をスムーズに放出してくれるんです。
寝ている間にかいた汗の湿気が、マットレス内部に留まることなく、効率よく外へ抜けていく。
まさに、湿度の高い日本の気候を徹底的に研究して生まれた、カビ対策の理想形とも言える構造ですね。
理由②:一般的なマットレスの約2倍!コイルが生む圧倒的な通気性
ネルマットレスの寝心地の核となっているのが、独立したコイルが体を点で支える「ポケットコイル」です。
ポケットコイルマットレスは、コイルとコイルの間に空間があるため、構造的に通気性が良いとされています。
そして、ネルマットレスがすごいのは、そのコイルの数です。
なんと、一般的なマットレスの約2倍もの小口径コイルを、贅沢に敷き詰めているんです。
例えばシングルサイズで1,173個、ダブルサイズでは1,734個ものコイルが内蔵されています。
コイルの数が多いということは、それだけ内部の隙間、つまり空気の通り道が多いということになります。
この「コイルリッチ構造」が、寝返りのしやすさだけでなく、マットレス内部の空気を常に入れ替えるポンプのような役割を果たし、圧倒的な通気性を生み出しているのです。
湿気がこもる暇を与えない、まさに風通しの良いマットレスだと言えますね。
理由③:定期的に裏返して使える「両面仕様」で湿気を分散
マットレスを長く清潔に使うための基本メンテナンスに「ローテーション」があります。
これは、頭側と足側を入れ替えたり、裏返したりすることで、同じ場所にばかり負荷や湿気が集中するのを防ぐためのものです。
しかし、最近のマットレスは寝心地を追求するあまり、片面しか使えない「片面仕様」のものが少なくありません。
その点、ネルマットレスは表裏どちらも同じ寝心地で使える「両面仕様」になっているのが、地味ながら非常に大きなメリットです。
重力がある以上、湿気はどうしてもマットレスの下の方へ溜まりがちです。
しかし、3ヶ月に一度など、定期的にマットレスを裏返してあげることで、底面に溜まろうとしていた湿気を解放し、カビのリスクを根本から分散させることができます。
これは湿気対策として非常に有効なだけでなく、コイルのへたりも均一にしてくれるため、結果的にマットレスの寿命を延ばすことにも繋がります。
理由④:防ダニ・抗菌・防臭機能を持つ高機能な綿生地を採用
マットレスの衛生面は、内部の構造だけでなく、私たちの肌に直接触れる側生地も重要ですよね。
ネルマットレスは、その点にも抜かりはありません。
側生地には、日本の大手繊維メーカーである帝人が開発した「TEIJIN MIGHTYTOP Ⅱ」という高機能な綿生地が採用されています。
この素材は、優れた防ダニ・抗菌・防臭効果を発揮するのが特徴です。
ダニを寄せ付けず、汗などによる細菌の増殖を抑え、気になるニオイの発生を防いでくれます。
カビとダニは、どちらも高温多湿の環境を好むため、繁殖する環境が似ています。
防ダニ効果があるということは、それだけ衛生的な状態を保ちやすいということ。
清潔な環境は、カビが繁殖しにくい環境づくりにも繋がります。
毎日安心して顔をうずめられる清潔さも、ネルマットレスの大きな魅力の一つですね。
他のマットレスと比べて通気性はどう違う?
では、他のタイプのマットレスと比べると、ネルマットレスの通気性はどのくらい優れているのでしょうか。
例えば、体圧分散性に優れる「低反発ウレタンマットレス」や、スポーツ選手にも人気の「高反発ファイバーマットレス」などがありますよね。
一般的に、ウレタン素材を主体としたマットレスは、コイルマットレスに比べて通気性が低い傾向にあります。
素材自体に隙間が少なく、熱や湿気がこもりやすいからです。
もちろん、最近ではウレタンに切り込みを入れるなどして通気性を高める工夫がされた製品も多くありますが、構造的に内部がほぼ空洞であるポケットコイルマットレスの通気性には、やはり敵いません。
そして、そのポケットコイルマットレスの中でも、ネルマットレスは「コイルの多さ」と「独自の13層構造」という2つの大きな武器を持っています。
通気性という観点においては、数あるマットレスの中でもトップクラスの実力を持っていると言って、まず間違いないでしょう。
【今日からできる】ネルマットレスの湿気・カビ対策【完全ガイド】

前の章では、直置きのデメリットを少し詳しくお伝えしたので、少し不安になってしまったかもしれませんね。
でも、ご安心ください。
これからご紹介する対策をしっかりと行えば、それらのデメリットはすべて回避することができます。
どれも難しいことではなく、「知っているか、知らないか」だけの差です。
ここでは、誰でも今日からすぐに始められる具体的な湿気・カビ対策を、網羅的にご紹介していきます。
一つの対策だけを完璧にやる、というよりは、いくつかの対策を組み合わせて行うことで、より効果が高まります。
ぜひ、ご自身のライフスタイルに合わせて、取り入れやすいものから実践してみてください。
対策①:マットレスを定期的に立てかけて換気する【最重要】
まず、数ある対策の中で最も重要で、かつ効果的なのが「マットレスを定期的に立てかける」ことです。
これはお金もかからず、一番シンプルな方法ですが、効果は絶大です。
なぜなら、マットレスの底面に溜まった湿気を、直接空気にさらして乾燥させることができるからです。
理想的な頻度としては、2〜3日に1回。
難しい場合でも、最低でも週に1回は行うように心がけたいところです。
朝起きたら、壁などにマットレスを立てかけて、数時間そのままにしておくだけでOKです。
その際、扇風機やサーキュレーターの風を当てると、さらに効率よく乾燥させることができますよ。
ネルマットレスは、一般的なポケットコイルマットレスの中では比較的軽量な設計になっていますが、それでも女性一人では少し大変かもしれません。
その場合は、半分に折りたたむようにして間に椅子などを挟み、底面が空気に触れるようにするだけでも効果があります。
毎日完璧にやろうとすると疲れてしまうので、無理のない範囲で習慣にすることが大切ですね。
対策②:「すのこ」や「除湿シート」を下に敷く
毎日のようにマットレスを立てかけるのは、正直ちょっと面倒…と感じる方も多いと思います。
そんな方におすすめなのが、「すのこ」や「除湿シート」といった便利アイテムの活用です。
もちろん、先ほどの「立てかける」習慣と組み合わせることで、効果は盤石になります。
「すのこ」は、床とマットレスの間に物理的な空間を作り、空気の通り道を確保してくれる役割があります。
一方、「除湿シート」は、マットレスから放出された湿気を、カビが発生する前に直接吸収してくれる役割を担います。
この二つは役割が違うので、どちらか一つというよりは、できれば両方使うのが理想的です。
「すのこ」で湿気が溜まりにくい環境を作りつつ、「除湿シート」で万が一の湿気も吸い取ってもらう、という二段構えの防衛策ですね。
これらを敷いておくだけで、日々の安心感がまったく違ってきますよ。
すのこベッド・すのこマットの選び方
すのこには、ベッドフレームのような高さのあるタイプから、床に敷くだけのマットタイプまで様々な種類があります。
直置きの手軽さを損ないたくない場合は、薄い「すのこマット」がおすすめです。
素材は、軽量で吸湿性に優れた「桐」が一般的ですが、防虫・防菌効果が期待できる「檜(ひのき)」なども人気です。
形状も、使わない時は丸めて収納できるロールタイプや、二つ折り・四つ折りにできるタイプなどがあります。
折りたたみタイプの中には、立ててそのまま布団干しとして使えるものもあり、非常に便利です。
選ぶ際のポイントは、ご自宅の床材を傷つけないように、裏面に緩衝材がついているかを確認すること。
また、自分の体重+マットレスの重量を支えられるだけの「耐荷重」があるかもしっかりチェックしましょう。
すのこを敷くことで、床からの底冷え対策にもなるので、冬場の快適性アップにも繋がります。
除湿シートの選び方と正しい使い方
除湿シートは、マットレスの下に敷くだけで、寝汗などの湿気をぐんぐん吸収してくれる心強い味方です。
選ぶ際にぜひチェックしてほしいのが、「吸湿センサー」の有無です。
これは、シートが湿気を吸収すると、センサーの色がブルーからピンクに変わるなどして、干すタイミングを知らせてくれる機能です。
これがあれば、いつ干せばいいのか一目で分かります。
また、天日干しすることで吸湿機能が復活し、繰り返し使えるタイプが経済的でおすすめです。
商品によっては、洗濯機で丸洗いできるものもあり、より清潔に使いたい方にぴったりです。
注意点として、除湿シートは湿気を吸いっぱなしだと、それ自体がカビの原因になってしまうこともあります。
吸湿センサーの色が変わったら、必ず天日干しをして、しっかりと乾燥させてから再び使うようにしてくださいね。
対策③:ベッドパッド・敷きパッドを活用して汗を防ぐ
カビ対策は、マットレスの「下」だけでなく、「上」も重要です。
マットレスに湿気が到達する前に、手前で食い止めるという考え方ですね。
そのために活用したいのが、「ベッドパッド」と「敷きパッド」です。
この二つは混同されがちですが、役割が少し違います。
ベッドパッドは、マットレスとシーツの間に敷き、寝汗や皮脂がマットレス本体に染み込むのを防ぐのが主な目的です。
一方、敷きパッドは、シーツの上に敷き、肌触りを良くしたり、温度調節をしたりするのが目的です。
どちらも汗を吸収してくれるので、湿気対策としては有効です。
これらはマットレス本体と違って、自宅で気軽に洗濯できます。
週に1回程度、シーツと一緒に洗濯する習慣をつければ、寝具全体を清潔に保つことができ、結果的にマットレスの湿気対策にも繋がります。
対策④:壁から5cm〜10cm離して設置する
これは意外と見落としがちなポイントですが、マットレスを設置する場所にも少し工夫が必要です。
お部屋のレイアウト上、壁際にマットレスを置くことが多いと思いますが、壁にピッタリとくっつけて置くのは避けましょう。
壁とマットレスの間に隙間がないと、そこでも空気が流れず、湿気がこもってしまいます。
その結果、マットレスの側面だけでなく、お部屋の壁紙にまでカビが広がってしまう、という悲しい事態を招くこともあります。
対策はとても簡単で、壁から5cmから10cmほど、こぶし一つ分くらいのスペースを空けてマットレスを置くだけです。
たったこれだけの隙間があるだけで、空気の通り道が生まれ、湿気がこもるのを大幅に防ぐことができます。
お部屋の掃除もしやすくなるというメリットもありますよ。
対策⑤:部屋自体の換気をこまめに行う
これまでマットレス周りの対策を中心にお話ししてきましたが、お部屋全体の環境を整えることも同じくらい大切です。
いくらマットレスの通気性を良くしても、寝室自体の湿度が高ければ、対策の効果は半減してしまいます。
特に、私たちが寝ている間は、呼吸や汗によって寝室の湿度はぐんぐん上がっていきます。
朝起きたら、まずは窓を開けて、部屋の空気を新鮮なものと入れ替える習慣をつけましょう。
理想は、対角線上にある2ヶ所の窓を開けて、空気の通り道を作ってあげることです。
窓が一つしかない場合は、換気扇を回したり、サーキュレーターで部屋の空気を循環させたりするだけでも効果があります。
日中、留守にする時間帯も、少しだけ窓を開けておくか、24時間換気システムをONにしておくなど、常に空気が動く状態を意識してみてください。
対策⑥:布団乾燥機を使って定期的に乾燥させる
雨が続いてなかなかマットレスを立てかけられない梅雨の時期や、日差しが弱く空気が冷たい冬場など、自然乾燥だけでは心もとない時もありますよね。
そんな時に大活躍するのが「布団乾燥機」です。
布団乾燥機を使えば、天候に関係なく、いつでも好きな時にマットレスを内側から温風でパワフルに乾燥させることができます。
湿気を飛ばしてくれるだけでなく、多くの布団乾燥機には「ダニ対策モード」も搭載されています。
高温の風でダニを死滅させることができるので、アレルギー対策としても非常に有効です。
また、冬場に寝る前に使えば、お布団がポカポカに温まり、気持ちよく眠りにつけるという嬉しい効果もあります。
少し初期投資はかかりますが、一台持っていると一年中、様々なシーンで役立つ便利な家電なので、導入を検討してみる価値は十分にあると思います。
ネルマットレスと人気のマットレスを徹底比較!あなたに合うのはどれ?

ここまでネルマットレスの魅力や直置きのポイントを解説してきましたが、「他の人気のマットレスと比べてどうなの?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。
マットレス選びは、決して安い買い物ではないからこそ、色々な商品を比較して、自分にとってベストな一枚を見つけたいですよね。
そこで、ここではネルマットレスに加えて、多くの方が比較検討されるであろう人気のマットレス4商品「エマスリープ」「コアラマットレス」「雲のやすらぎプレミアム」「モットン」をピックアップ。
「直置きできる?」「清潔に使える?」という、皆さんが特に気になるであろう2つの視点から、各マットレスを中立的な立場で徹底的に比較していきます。
この記事を読めば、それぞれのマットレスの特徴がクリアになり、あなたにぴったりの一枚がきっと見つかるはずです。
| 商品名 | 特徴 | 構造 | 素材 | 価格帯 | 通気性・防臭抗菌性能 | 硬さ | 返品・交換・トライアル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【NELL マットレス】 |
高密度ポケットコイルで体圧分散に優れ、寝返りしやすい設計 | ポケットコイル+ウレタンフォーム | 高密度ポケットコイル、ウレタンフォーム | 約75,000円~ | 通気性良好、防カビ・抗菌加工あり | 中程度 | 120日間トライアル、10年保証 |
| エマスリープ | 3層構造で体圧分散と通気性を両立 | 3層ウレタンフォーム | エアグリッド、HRXフォームなど | 約98,000円~ | 通気性高く、抗菌カバー使用 | 中程度 | 100日間トライアル、10年保証 |
| コアラマットレス | 振動吸収性に優れ、パートナーの動きを感じにくい | 3層ウレタンフォーム | クラウドセル、テンセルリヨセル繊維 | 約82,000円~ | 通気性良好、抗菌カバー使用 | 表裏で硬さ調整可能 | 120日間トライアル、10年保証 |
| 雲のやすらぎプレミアム
|
5層構造で体圧分散性と保温性を両立 | 5層ウレタンフォーム | 高反発ウレタン、羊毛など | 約39,800円~ | リバーシブル設計で通気性と保温性を調整、防ダニ・抗菌加工あり | やや柔らかめ | 100日間返金保証 |
| 腰痛対策マットレス【モットン】
|
高反発ウレタンで腰痛対策に特化 | 単層ウレタンフォーム | ナノスリー高反発ウレタン | 約39,800円~ | 通気性高く、防ダニ・抗菌加工あり | 硬さ3種類から選択可能 | 90日間トライアル、14日以内返品可 |
| 眠りの世界に品質を【エアウィーヴ公式オンラインストア】
|
エアファイバー素材で高い通気性と体圧分散性 | エアファイバー | ポリエチレン樹脂 | 約66,000円~ | 通気性抜群、カバーと中材洗濯可能 | やや硬め | 30日間返品保証 |
| 「睡眠の質を整える」快眠マットレス!昭和西川のムアツ
|
凹凸構造で体圧を点で支える | 2層ウレタンフォーム | ウレタンフォーム(抗菌加工) | 約49,500円~ | 通気性良好、抗菌・防臭加工あり | やや硬め | 返品保証なし |
まずは比較する5つのマットレスの基本情報をチェック
本格的な比較に入る前に、今回登場する5つのマットレスが、それぞれどんな製品なのか、基本的なスペックを簡単におさらいしておきましょう。
マットレスと一口に言っても、構造や素材が異なると、寝心地や通気性も大きく変わってきます。
ネルマットレスは、内部にたくさんのバネ(コイル)が入った「ポケットコイル式」です。
一方で、今回比較する他の4つの商品は、いずれも高反発ウレタンフォームを主体とした「ウレタン式」のマットレスです。
この構造の違いが、比較する上で一つの大きなポイントになります。
価格帯や保証期間も様々ですので、まずは全体像をざっくりと掴んでみてください。
【比較①:直置き対応】床に直接敷けるのはどれ?各社の見解まとめ
まず最も気になる「直置き」についてですが、結論から言うと、今回比較する5つのマットレスは、すべて「適切な対策をすれば直置き可能」という点で共通しています。
どのメーカーの公式サイトや紹介記事を見ても、「敷きっぱなしはNG」「すのこや除湿シートを使ってください」「定期的に立てかけて換気してください」といった注意喚起が必ず記載されています。
これは、マットレスの構造がコイル式かウレタン式かに関わらず、床との間に湿気が溜まるリスクは等しく存在するからです。
特にウレタンフォームは、一度湿気を吸うと乾きにくい性質があるため、むしろコイルマットレス以上に日々のメンテナンスが重要になるとも言えます。
「このマットレスだから直置きしても大丈夫」という製品は存在しません。
どのマットレスを選ぶにせよ、この記事の前半でご紹介したような湿気・カビ対策は、快適な睡眠のために必須の習慣だと考えておきましょう。
【比較②:清潔機能】防カビ・防臭・防ダニ性能で選ぶなら?
次に、マットレスを長く清潔に保つための「防カビ・防臭・防ダニ」といった機能について比較してみましょう。
この点については、各社で少し対応が分かれます。
まず「ネルマットレス」と「雲のやすらぎプレミアム」は、側生地(カバー)に帝人が開発した高機能綿「マイティトップⅡ」を採用しているのが大きな特徴です。
これは、素材そのものに高い防ダニ・抗菌・防臭効果が備わっているため、特別な対策をしなくても衛生的な状態を保ちやすいというメリットがあります。
次に「コアラマットレス」ですが、こちらは一部の上位モデルで、ウレタンフォームに消臭・抗菌効果のある竹炭を配合するなどの工夫が見られます。
一方で、「エマスリープ」と「モットン」は、マットレス本体には特に防ダニや抗菌といった機能は付加されていません。
その代わり、カバーは取り外して洗濯が可能なので、こまめに洗うことで清潔さを保つという考え方です。
もちろん、どのマットレスも別売りの防水・防ダニ機能があるシーツやプロテクターを併用することで、清潔機能を追加することは可能です。
【結論】タイプ別!あなたにおすすめのマットレス診断
これまでの比較を踏まえて、あなたがどんなポイントを重視するかによって、おすすめのマットレスは変わってきます。
・通気性と衛生面を両立させたいなら「ネルマットレス」 or 「雲のやすらぎプレミアム」
コイル構造で通気性が良く、さらに防ダニ・抗菌防臭機能も標準で欲しい、という方にはこの2つが有力候補です。
特に寝返りのしやすさを重視するならネルマットレスがおすすめです。
・振動の伝わりにくさと寝心地のフィット感を求めるなら「エマスリープ」 or 「コアラマットレス」
ウレタンフォームは、コイルと違って振動が伝わりにくいのが特徴です。
二人で寝る方や、体にフィットするような寝心地が好きな方は、こちらを検討してみると良いでしょう。
・まずは価格を抑えて高反発マットレスを試してみたいなら「モットン」
腰痛対策マットレスとして人気があり、比較的手頃な価格から始められるのが魅力です。
シンプルな機能で、まずはウレタンマットレスの寝心地を試してみたいという方に合っています。
中立的に比較してわかるネルマットレスの魅力
こうして他の人気商品と客観的に比較してみると、ネルマットレスの独自の立ち位置がよくわかりますね。
多くのブランドがウレタンフォームを主体とする中で、あえて通気性に優れる「ポケットコイル」構造を採用している点。
そして、日本の多湿な気候を見据えて、マットレス本体に標準で「防ダニ・抗菌・防臭」という清潔機能をしっかりと持たせている点。
これは、単に寝心地が良いだけでなく、「一年を通して、長く安心して清潔に使い続けてほしい」というメーカーの強い意志の表れだと私は思います。
もちろん、ウレタンマットレスのフィット感や価格の手頃さも大きな魅力です。
最終的には、ご自身の好みやライフスタイル、そして何を一番大切にしたいかで選ぶのが一番です。
この比較が、あなたのベストな一枚を見つけるための、良いヒントになれば嬉しいです。
ネルマットレスの直置きなど使い方に関するQ&A

さて、ここまでネルマットレスを直置きで快適に使うためのデメリットや対策、そしてネルマットレス自体の魅力について詳しく解説してきました。
記事の最後に、これまでの内容で触れられなかった細かい疑問や、「こういう場合はどうなんだろう?」と多くの方が感じそうな点について、Q&A形式でお答えしていきたいと思います。
購入前の最後の不安や、実際に使い始めてから出てくる疑問を、ここでスッキリ解消しておきましょう。
Q. ネルマットレスの下に布団を敷くのは効果ありますか?
冬場の底冷え対策や、寝心地を柔らかくするため、マットレスの下に今使っている敷布団を敷こうかな、と考える方もいるかもしれません。
ですが、結論から言うと、これは全くおすすめできません。
むしろ、カビのリスクを高めてしまう逆効果な方法です。
なぜなら、敷布団が寝汗などの湿気を吸い込み、ネルマットレスと床との間で湿気の巨大な温床になってしまうからです。
また、せっかくのネルマットレスの優れた通気性も、布団によって完全に塞がれてしまい、その性能を全く活かせなくなってしまいます。
もし底冷えが気になる場合は、布団ではなく、すのこを敷いた上で、さらにその上に断熱シートや厚手のラグなどを敷くのが効果的です。
寝心地を変えたい場合は、マットレスの上に敷きパッドや薄手のマットレストッパーなどを重ねるようにしてください。
Q. 直置きで使った場合、120日間の返金保証や10年保証は対象になりますか?
これは購入を検討している方にとっては、非常に重要な問題ですよね。
ご安心ください。
直置きで使っていたとしても、この記事でご紹介したような適切な湿気対策をきちんと行い、通常の使用範囲で寝心地に不満があったり、マットレスにへたりが生じたりした場合は、もちろん保証の対象となります。
メーカー側も、日本の住宅事情を考えれば直置きで使われるケースがあることは想定しているはずです。
ただし、注意していただきたいのは、明らかにメンテナンスを怠ったことが原因で発生したカビや、お客様自身の過失による汚れ、破損などについては、保証の対象外と判断される可能性が高いという点です。
これはどんな製品でも同じですよね。
大切なマットレスを長く使うため、そして万が一の際に保証をしっかりと受けられるようにするためにも、日々の適切なお手入れを心がけましょう。
Q. フローリングと畳、直置きするならどちらが良いですか?
これもよくある疑問の一つですね。
フローリングと畳、どちらも一長一短があります。
フローリングは、表面が硬く平らなのでマットレスが安定しやすい反面、通気性が全くなく、湿気がダイレクトに結露しやすいというデメリットがあります。
特に冬場の底冷えはかなり厳しいものがあります。
一方、畳は、原料であるい草が呼吸するため、ある程度の調湿効果が期待できます。
しかし、それはあくまで「フローリングよりはマシ」というレベルの話です。
畳自体が湿気を吸い込みすぎてしまうと、今度は畳の方にカビが生えてしまうリスクがありますし、一度カビが生えると除去は非常に困難です。
結論としては、「どちらの床材であっても、すのこや除湿シートを下に敷く、という基本的な対策は絶対に必要」ということです。
対策さえしっかりすれば、どちらの床でも快適に使えますので、お部屋の環境に合わせて選んでいただければ問題ありません。
Q. 万が一カビてしまった場合の対処法は?
考えたくないことですが、もしカビが生えてしまった場合の対処法も知っておきましょう。
まず、残念ながら、マットレスの内部深くまで根を張ってしまったカビを、自力で完全に除去するのはほぼ不可能です。
あくまで応急処置になりますが、表面に生えたばかりの軽いカビであれば、市販の消毒用エタノールを布に含ませて、ポンポンと叩くように拭き取る方法があります。
その後、風通しの良い場所で完全に乾燥させることが重要です。
ただし、生地を傷めたり、変色させたりするリスクもあるので、目立たない場所で試してからにしてください。
より本格的に対処したい場合は、マットレス専門のクリーニング業者に依頼するという手もありますが、費用は数万円と高額になることが多いです。
やはり、カビは「生えてからどうにかする」のではなく、「生やさないための予防」が何よりも大切だということですね。
Q. すのこさえ敷けば、毎日立てかけなくても大丈夫ですか?
「すのこを敷けば、もう安心!」「これで面倒な立てかけ作業から解放される!」と思いたい気持ちは、とてもよく分かります。
しかし、答えは「いいえ、それでも定期的に立てかけるのが理想です」となります。
すのこは、あくまで床とマットレスの間に隙間を作り、空気の通り道を確保するための「補助アイテム」です。
湿気が溜まりにくい環境は作ってくれますが、マットレス内部に溜まった湿気を積極的に外に追い出してくれるわけではありません。
特に、常に体重がかかって圧縮されているマットレスの中央部分などは、どうしても湿気がこもりやすくなります。
毎日立てかけるのが難しい場合でも、最低でも週に1回、できれば2〜3回に1回はマットレスを壁に立てかけるなどして、底面に風を当ててあげる時間を作ってあげてください。
その一手間が、結果的にマットレスの寿命を延ばし、長く快適な睡眠を守ることに繋がります。
Q. ネルマットレスに合うベッドフレームはどのようなものですか?
ネルマットレスは様々なタイプのベッドフレームに合わせることができますが、最も相性が良いのは「すのこタイプ」のベッドフレームです。
すのこはマットレスとの間に空気の通り道を作ってくれるため、ネルマットレスが持つ高い通気性を最大限に活かすことができます。
ベッドフレームを選ぶ際は、必ず「耐荷重」を確認してください。
「ベッドフレームの耐荷重」が「ネルマットレスの重量+使用者の体重」を上回っていることが安全に使うための絶対条件です。
もちろん、マットレスとフレームのサイズが合っているかもしっかり確認してくださいね。
Q. ネルマットレスはすのこを使用しても良いですか?
はい、もちろんです。
むしろ、直置きをする場合や、ベッドフレームの床板が板状になっている場合には、すのこの使用を強く推奨します。
この記事で繰り返しお伝えしている通り、マットレスにとって湿気は大敵です。
すのこを一枚敷くだけで、マットレスの底面に湿気がこもるのを劇的に改善できます。
床に直接敷くタイプの「すのこマット」や、ベッドフレームの床板がすのこになっている「すのこベッド」など、様々なタイプがありますので、ご自身の環境に合わせて取り入れてみてください。
Q. ネルマットレスの表裏・上下はどのように違いますか?
ネルマットレスは、どちらの面も同じ寝心地で使える「両面仕様」です。
そのため、表と裏に違いはありません。
これはマットレスを長持ちさせる上で非常に大きなメリットで、3ヶ月に一度など、定期的にマットレスを裏返して使うことで、湿気が同じ面に溜まるのを防ぎ、へたりを均一にすることができます。
また、上下(頭側と足側)についても、定期的に入れ替えてローテーションすることで、特定の部分にばかり負荷がかかるのを防ぎ、より長く快適な寝心地を保つことができます。
Q. ネルマットレスは無印のベッドフレームの上に置いて使えますか?
はい、サイズが合い、耐荷重の条件を満たしていれば問題なくご使用いただけます。
無印良品のベッドフレームは、シンプルなデザインで人気があり、すのこ仕様のものも多いため、ネルマットレスとの相性も良いと言えます。
ご購入前には、無印良品のウェブサイトや店舗で、検討しているベッドフレームの「耐荷重」と「寸法」を必ずご確認ください。
その上で、使用したいネルマットレスのサイズ・重量(例:シングルサイズで22.0kg)と、ご自身の体重を足した数値が耐荷重の範囲内に収まっているかを確認すれば、安心して組み合わせることができます。
Q. ネルマットレスは子供や赤ちゃんにも使えますか?
ある程度身体が大きくなったお子様であれば、寝返りのしやすいネルマットレスは快適な睡眠をサポートできるかと思います。
また、側生地には防ダニ・抗菌・防臭機能のある素材が使われているため、衛生面でも安心感が高いです。
ただし、「赤ちゃん(特に新生児や乳幼児)」への使用は注意が必要です。
赤ちゃんには、顔が沈み込んで窒息するのを防ぐため、ベビーベッド用の硬めの布団(ベビー布団)が推奨されています。
ネルマットレスは大人用に設計された寝心地ですので、赤ちゃんへの使用については、安全性を最優先に慎重にご判断いただく必要があります。
Q. ネルマットレスは4人家族でどのように使えばいいですか?
4人家族で川の字になって寝る場合、ネルマットレスを2台連結して使うのが一般的です。
例えば、以下のような組み合わせが考えられます。
・シングル(幅95cm)を2台 → 合計幅190cm(キングサイズ相当)
・セミダブル(幅120cm)を2台 → 合計幅240cm
・ダブル(幅140cm)を2台 → 合計幅280cm
ご家族の体格や寝室の広さに合わせて、最適な組み合わせを選んでみてください。
マットレス同士の間にできる隙間が気になる場合は、市販の「すきまパッド」を挟んだり、2台まとめて覆うことができる大きなサイズのボックスシーツやベッドパッドを使ったりすると、隙間が気にならなくなり、より快適になりますよ。
Q. ネルマットレスは電気毛布を使っても大丈夫ですか?
はい、ご使用いただけます。
ただし、長時間の高温での使用は、マットレス内部のウレタンフォームなどの素材を傷め、劣化を早めてしまう可能性があります。
そのため、就寝前に寝具を温めておく目的で使用し、眠る時にはスイッチを切るか、タイマーを設定するのがおすすめです。
また、電気毛布の取扱説明書にも、マットレスの上での使用に関する注意点が記載されている場合がありますので、そちらも併せてご確認いただくと、より安心です。
Q. ネルマットレスを2段ベッドの上で使えますか?
残念ながら、2段ベッドの「上段」での使用は推奨できません。
ネルマットレスは厚さが21cmあります。
多くの2段ベッドは、上段からの転落を防ぐ安全柵の高さを確保するため、使用できるマットレスの厚さに10cm前後といった制限を設けています。
厚みのあるネルマットレスを使用してしまうと、安全柵が本来の高さを保てなくなり、大変危険です。
2段ベッドの「下段」であれば、高さの制限はありませんので問題なくご使用いただけます。
まとめ:正しい対策でネルマットレスを床に直置きして快適な睡眠を
結論として、ネルマットレスの直置きは「正しい対策」をすれば全く問題なく、快適に使うことができます。
そのための最も重要な対策は、
①最低でも週に1回はマットレスを立てかけて、底面に風を通すこと。
②補助アイテムとして「すのこ」と「除湿シート」を活用し、湿気の逃げ道を作ってあげること。
この2つを実践するだけでも、カビのリスクは劇的に減らすことができます。
それに加えて、ネルマットレスは一般的なマットレスの約2倍のコイル数を誇るなど、構造そのものが非常に通気性に優れています。
つまり、「万全の湿気対策」と「マットレス自体の高い性能」という二つの要素が合わさることで、安心して直置きライフを送ることができるのです。
ベッドフレームをなくすことで得られる、お部屋の開放感や掃除のしやすさといったメリットを享受しながら、ネルマットレスが提供する最高の寝心地を、ぜひ体験してみてください。
もし、まだ少し不安が残るという方も、ネルマットレスには120日間じっくり自宅で試せるフリートライアル期間があります。
まずは一度、その寝心地と、直置きでの使いやすさを、ご自身の体で確かめてみてはいかがでしょうか。
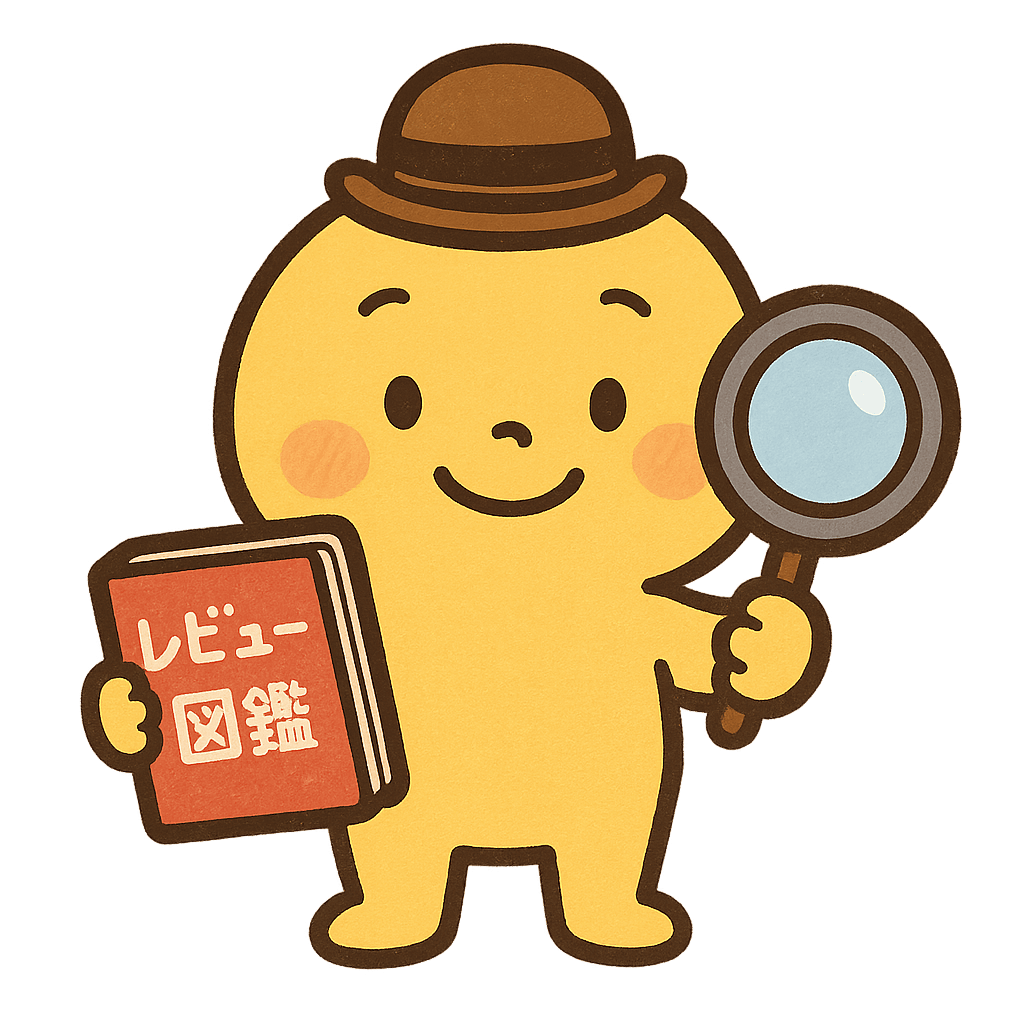
今回、ネルマットレスの直置きについてとことん調べてみて改めて感じたのは、「やっぱり、どんなに良い製品でも使う側のちょっとした工夫や愛情って大切だな」ということでした。
ネルマットレス自体、通気性についてものすごく考え抜かれて作られています。
でも、やっぱり日本のジメジメした気候の中で「敷きっぱなし」は、さすがに酷ですよね。
ほんの少し、朝起きた時に「よっこいしょ」と立てかけてあげるだけで、マットレスは長持ちして最高の寝心地を返してくれる。
なんだか、モノと人との良い関係性を築くヒントが、この「直置き」というテーマには詰まっているような気がします。
皆さんもぜひ、ネルマットレスと良いパートナーシップを築いて、快適な睡眠ライフを送ってくださいね。